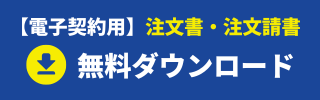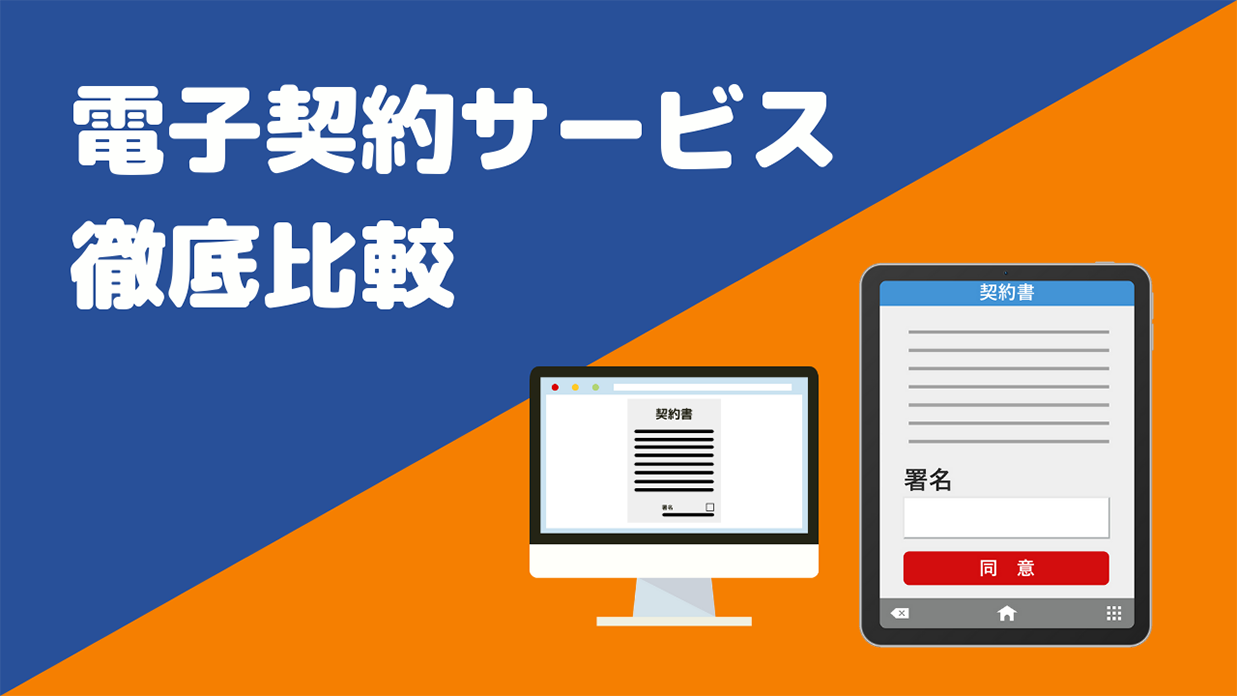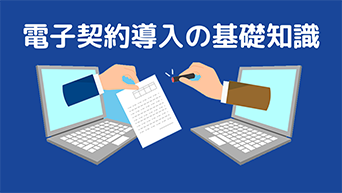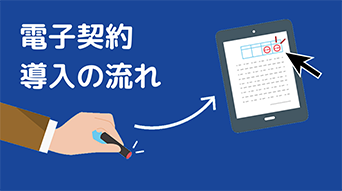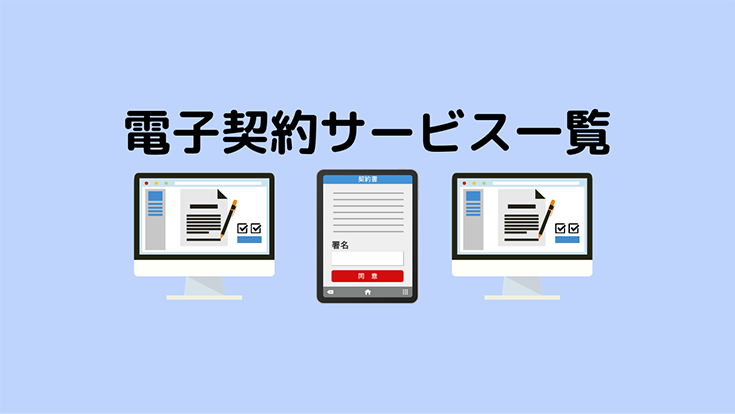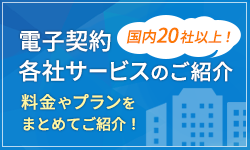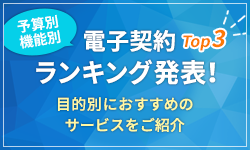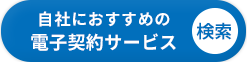2024年08月29日2025年11月21日
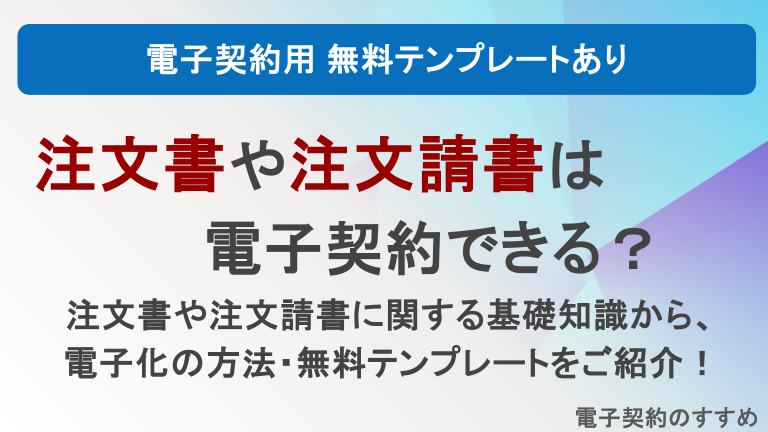
注文書と注文請書について
注文書とは、買主が売主に対して商品やサービスの購入を正式に依頼するための文書で、後続の請書、納品書、請求書などの根拠にもなるので、取引の基礎として重要な文書です。
対して、注文請書は、売主が買主からの注文を受けて、その内容を確認し受諾したことを示すビジネス取引において重要な役割を果たす文書です。
注文書と発注書、注文請書と発注請書は、微妙な違いはあるものの、実務上ほぼ同じ意味で、互換的に使われることが多く、業界や文脈等によって使い分けられています。
注文書と注文請書の違い
【発行者】
- ・注文書:注文者(買主)が発行
- ・注文請書:受注者(売主)が発行
【目的】
- ・注文書:商品やサービスの購入を正式に依頼
- ・注文請書:注文の受諾を確認し、取引条件を承諾
【作成のタイミング】
- ・注文書:注文者が取引の開始時に作成
- ・注文請書:受注者が注文書を受け取った後に作成
【内容】
- ・注文書:商品詳細、価格、数量、納期などを記載
- ・注文請書:注文内容と注文内容に対する承諾を示す
【法的な意味】
- ・注文書:注文者(買主)による商品やサービスの購入依頼や申込みの意思表示
- ・注文請書:受注者(売主)による注文内容への承諾の意思表示
【契約成立】
- 注文書のみでは契約は成立しないため、注文請書が発行されることで、一般的に契約が成立するものとなります。
※契約の確実な成立には、化注文書に対する承諾(注文請書など)を得ることが重要
注文書に記載する基本項目
注文書は、注文内容の確認や事務手続きのためだけの書類ではなく、言った・言わないなどのトラブルを防ぐための「証拠」であり、何を・いつまでに・何個・いくらで、など、売買の「約束事」を明確にする役割を担っています。 具体的にどのような項目を記載したらよいか、以下で紹介します。
注文書の項目例
| 1 | 書類タイトル |
|---|---|
| 2 | 注文書番号 |
| 3 | 発行日 |
| 4 | 発注者情報 |
| 5 | 受注者情報 |
| 6 | 注文内容(品名・数量・単価・金額) |
| 7 | 合計金額 |
| 8 | 納期(納品希望日) |
| 9 | 納品場所 |
| 10 | 支払い条件 |
| 11 | その他特記事項・備考 |
| 12 | 発注者署名欄・捺印欄 |
1.書類タイトル
書類の種類を示す「注文書」を明確に記載します。
2.注文書番号
注文書を一意に識別するための管理用の番号を付与します。これにより、後の問い合わせや照合が容易になり、管理が効率化されます。同じ取引の見積書や請求書などと紐付けるとより便利です。
3.発行日
この注文書が作成・発行された日付を明記します。
4.発注者情報
発注元の名称(企業名または個人名)、所在地、電話番号、担当者名、部署などを記載します。連絡先が明確であることが重要です。
5.受注者情報
注文を受ける側の企業名または個人名、住所、電話番号などを記載します。「御中」や「様」を付記し、敬意を示します。
6.注文内容(品名・数量・単価・金額)
最も重要な項目であり、注文の具体的な中身を正確に記載します。
例)
| 品名/サービス名 | 型番/詳細 | 数量 | 単位 | 単価(税抜) | 金額(税抜) |
|---|---|---|---|---|---|
| ××××製品 | ABC-123 | 5 | 個 | 10,000円 | 50,000円 |
| システム開発 | (別途仕様書) | 1 | 式 | 300,000円 | 300,000円 |
| 小計 | 350,000円 | ||||
| 消費税 | 35,000円 | ||||
| 合計 | 385,000円 |
7.合計金額
上にあるように、注文内容の「小計+消費税=総額」の形で明記します。
8.納期(納品希望日)
注文した物品の納品を希望する期日、またはサービスの完了を希望する期日を記載します。
9.納品場所
商品やサービスを届けてほしい場所を明記します。ビル名や部署まで含めることで誤配送を防げます。
10.支払い条件
代金の支払い方法、支払い期日、支払い回数(一括払いか分割払いか)などを記載します。振込手数料の負担についても明記することが望ましいです。
11.その他特記事項・備考
保証期間、検収条件、契約不適合責任、秘密保持など、取引に関連する補足的な取り決めがある場合はここに記入します。
12.発注者署名欄・捺印欄
発注者の署名または会社印を押す欄です。注文書としての正式な効力を持たせるために必要です。
注文請書に記載する基本項目
注文請書は、発注者から送られてきた注文書の内容を確認し、その注文を正式に引き受ける意思表示をするために発行する書類です。ただし、発行義務がなく、特に定められたフォーマットもありませんが、記入して欲しい項目はあるため、具体的にどのような項目を記載したらよいか、以下で紹介します。
注文請書の項目例
| 1 | 書類タイトル |
|---|---|
| 2 | 注文請書番号(管理番号) |
| 3 | 発行日 |
| 4 | 受注者情報 |
| 5 | 発注者情報 |
| 6 | 受注内容(品名・数量・単価・金額) |
| 7 | 合計金額 |
| 8 | 納期(納品予定日) |
| 9 | 納品場所 |
| 10 | 支払い条件 |
| 11 | その他特記事項・備考 |
| 12 | 受注者署名欄・捺印欄 |
1.書類タイトル
「注文請書」「発注請書」などと明確に記載します。
2.注文請書番号(管理番号)
注文請書を一意に識別するための番号を付与します。
3.発行日
注文請書が作成された日付を記載します。
4.受注者情報
先ほどの注文書とは順番が逆で、注文を引き受けた側の企業情報を記載します。
5.発注者情報
注文を出した側の企業名または個人名、住所などを記載します。「御中」や「様」を付記し、敬意を示します。
6.受注内容(品名・数量・単価・金額)
注文書の内容を転記。
7.合計金額
注文書の内容を転記。
8.納期(納品予定日)
注文書の内容を転記。注文書に記載された納期を承諾する形で記載します。納期について調整が必要な場合は、事前に発注元と協議し、合意した上でこの項目に記載します。
9.納品場所
注文書の内容を転記。注文書に記載された納品場所を承諾する形で記載します。
10.支払い条件
注文書の内容を転記。注文書に記載された支払い条件を承諾する形で記載します。
11.その他特記事項・備考
注文書に記載された特記事項を請書でも改めて確認する意味で記載することもあります。
12.受注者署名欄・捺印欄
これにより、注文の内容を正式に引き受けたことを示します。
注文書や注文請書に収入印紙は必要?
注文書は基本的に課税対象となりませんが、注文請書は、内容により印紙税が必要となるケースがあります。
収入印紙を貼る必要があるかどうかは、その書類が印紙税法で定められた「課税文書」に該当するかどうかで決まります。特に注文請書の場合、「請負に関する契約書」とみなされるかどうかが重要なポイントになります。
注文請書に収入印紙が必要となるケース
印紙税法でいう「請負」とは、簡単に言えば「ある仕事の完成を約束し、その結果に対して報酬を受け取る」という内容の契約のことです。以下のような取引の場合には、注文請書が「請負に関する契約書(第2号文書)」と判断され、収入印紙が必要となる可能性があります。
※取引例)
・システムの開発、Webサイトの制作
・広告物のデザイン、コンテンツ制作(記事・写真・イラストなど)
・物品の製造や加工
・建物の建築や土木工事、リフォーム
・スポット的な特定の修理や保守点検(期間ではなく個別の作業請負の場合)
これらの取引で、発注側が「この内容でお願いします」と注文書を送り、それに対して受注者側が「確かに承知いたしました」と注文請書を出す。
このような請負の場合、両方の書類が揃って契約の成立を証明する「契約書」としての役割を持つとみなされ、課税対象となります。
注文請書の印紙税額
| 注文請書に記載されている契約金額 | 税額 |
|---|---|
| 1万円未満のもの | 非課税 |
| 1万円以上100万円以下のもの | 200円 |
| 100万円を超え200万円以下のもの | 400円 |
| 200万円を超え300万円以下のもの | 1,000円 |
| 300万円を超え500万円以下のもの | 2,000円 |
| 500万円を超え1,000万円以下のもの | 1万円 |
| 1,000万円を超え5,000万円以下のもの | 2万円 |
| 5,000万円を超え1億円以下のもの | 6万円 |
| 1億円を超え5億円以下のもの | 10万円 |
| 5億円を超え10億円以下のもの | 20万円 |
| 10億円を超え50億円以下のもの | 40万円 |
| 50億円を超えるもの | 60万円 |
| 契約金額の記入のないもの | 200円 |
注文書と注文請書は電子契約できる?
注文書と注文請書は、特に法律で「書面(紙)でなければならない」などは定められていないので、電子契約を行うことが可能です。 注文書、注文請書のどちらも、契約金額が10万円を超える場合には、課税文書の対象となり、印紙税も発生しますので、電子契約で行うことで印紙税の削減が可能です。
※契約金額が10万円以下の場合や特定の業種や取引では非課税となる場合もありますので、詳しくは専門家にご相談下さい。
注文書や注文請書を電子契約用に変更する方法
注文書や注文請書は基本的に見積書のようなフォーマットで作成されていることが多いため、基本的には大きく変更する必要がないパターンが多く、電子契約で不要となる「押印」のための押印欄を削除する 等、簡単な調整で電子契約用に変更が可能です。
※電子契約では、押印・捺印は不要となるため、電子契約サービスを使用する場合には書面から、押印・捺印の箇所は削除しても問題ありません。
他、もし注文書や注文請書内に、「書面による承諾」や「本契約成立の証として、各自押印の上~」等の表記がある場合には、以下の内容への変更をおすすめいたします。
●「書面による承諾」等の記載がある箇所の文言を変更
例:書面:書面による承諾が無い限り
電子契約:書面または双方が合意した電磁的措置による承諾が無い限り
●末尾文言(本契約の成立の証として、以降)を変更
例:書面:本書2通を作成し、各自記名押印の上、各1通ずつ保有する。
電子契約:本電子契約書ファイルを作成し、それぞれが電子署名を行う。
なお、本契約においては、電子データである本電子契約書ファイルを原本とし、
同ファイルを印刷した文書はその写しとする。
【電子契約用】注文書と注文請書の無料テンプレート
ここまで、注文書と注文請書の電子化についてご紹介しましたが、いかがでしたでしょうか?
既に自社の文書がある方は、内容を少し調整するだけで簡単に電子契約が可能です。
当サイトでは、電子契約用に調整した契約書テンプレートをご用意しておりますので、これから自社用の注文書や注文請書をを作成をされる方は、ぜひご活用下さい!
※上記ファイルは、あくまでも電子契約用に調整した契約書のサンプルとなりますので、ご利用については弊社では責任を負いかねます。必ず専門家へご相談頂き、内容を自社用に変更・カスタマイズした上でご使用下さい。
注文書と請書のよくある質問
注文書はいつ、だれが作る?
(基本的な発行タイミング・注文書は発注者が作ること等を説明)
→注文書は、取引内容が確定したタイミングや見積書の確認後に発行されます。また、発注者(商品やサービスを依頼する側)が作成します。
注文請書はいつ、だれが作る?
注文請書は、基本的に注文書を受け取った後に発注内容を確認した後で、受注者(依頼を受けた側)が作成します。
【国税庁ホームページ:課税文書の作成時期及び作成者】
注文書や注文請書の発行は必須?
法律上、注文書や注文請書の発行は義務ではありません。ただし、取引内容や合意事項を明確にし、トラブルを防ぐために、文書として残すのがおすすめです。
注文請書は発注者側で作成しても問題ない?
注文請書は本来、受注者が発行するのが一般的ですが、内容に誤りがなければ発注者側で作成しても法律上、問題ありません。ただし、必ず受注者の確認・署名や押印を得ることが重要です。
注文書に記載する納品先と注文者が違っても大丈夫?
はい、問題ありません。 注文者(契約当事者)と納品先が異なるケースはよく見られます。例えば、親会社が子会社のために発注する、建設現場に直接資材を届ける、といったときです。注文書に「注文者」と「納品先」をそれぞれ明確に記載することが重要です。
注文書や注文請書の保管期間は?
注文書や注文請書の法定保管期間は原則7年間(事業年度の確定申告書提出期限の翌日から数えて7年間)です。これは会社法や法人税法に基づくもので、取引の証拠書類として用いられるためです。電子データでの保管も要件を満たせばOKです。
注文書に有効期限を設けられる?
はい、設定することができます。 注文書に有効期限を明記することで、価格や条件の変更を防ぎます。「本注文書の有効期限は発行日より7日間とします」といった記載が一般的です。期限内に受注者からの返答がなければ、この注文は無効になることを示せます。
注文請書の印紙はどちらが負担する?
印紙税の負担者は課税文書を作成した側が原則負担します。つまり、この場合は、注文請書を作成する受注者が負担するのが一般的です。ただし、契約次第で発注者と分担するなど、負担分を変えられます。
【国税庁ホームページ:課税文書の作成時期及び作成者】
注文請書の印紙を貼り忘れたらどうなる?
印紙の貼り忘れは、印紙税法違反となり、ペナルティが科せられる可能性があります。税務調査で指摘された場合は、本来の印紙税額の2倍に相当する過怠税が加算され、合計で3倍の税金を支払うことになります。意図的なものでなくても対象となります。
【国税庁ホームページ:印紙を貼り付けなかった場合の過怠税】
注文書や注文請書は、電子化できる?
はい、電子化は可能です。 書面ではなくPDF化してメールで送付したり、クラウドサービスを利用したりする方法があります。法的効力を持たせつつ証拠力を高めるなら、電子署名を用いた電子契約サービスの活用がおすすめです。
電子契約で、注文書と注文請書をまとめて送っても問題ない?
はい、問題ありません。 むしろ効率的でおすすめです。注文書と注文請書を1つのPDFファイルなどにまとめ、電子契約サービスで一括送信・締結することで、やり取りの手間が省け、契約プロセスがスムーズになります。印紙税もかからず、双方の管理も楽になります。
電子契約書はなぜ印紙税がかからないの?
印紙税のルールは、もともと「紙の書類」が中心だった明治時代に作られました。そのため、税金がかかる対象となる「課税文書」は紙媒体に限定されています。デジタルの世界でやり取りされる電子契約書は、この「紙の文書」には当たらないため、印紙税を納める必要がありません。国税庁からも認められています。
(国税庁ホームページ:コミットメントライン契約に関して作成する文書に対する印紙税の取扱い)
電子契約サービスの選び方
電子契約をこれから選ぶ方は以下ページもぜひご覧ください!