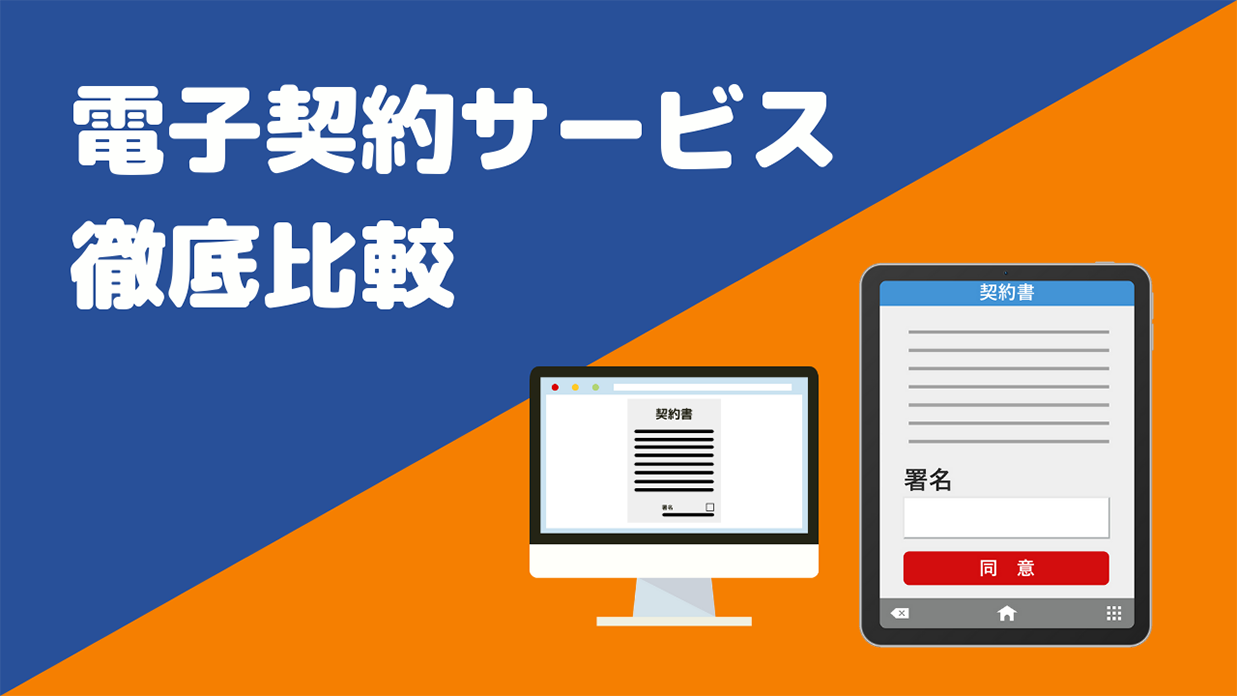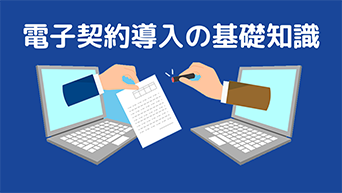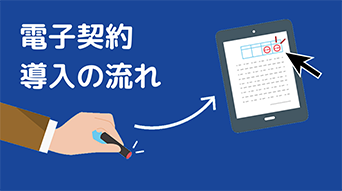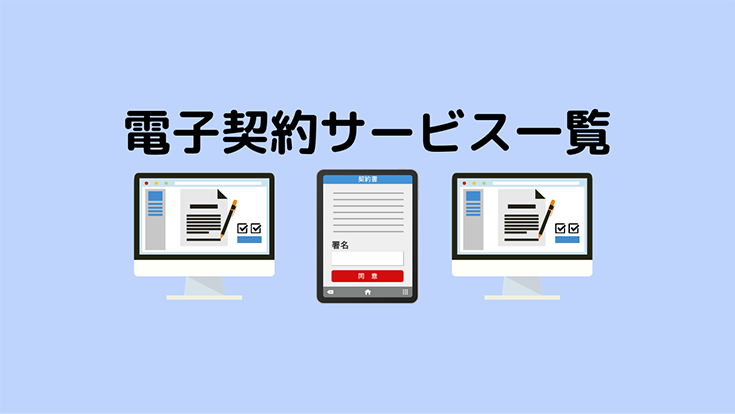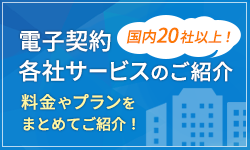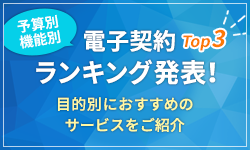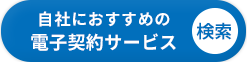おきたい
電子契約の基礎知識
リモートワークの促進以降、脱ハンコによる業務効率化・
感染症対策の手段として、ますます注目の集まる電子契約。
とはいえ「電子契約って何」という方もまだまだ多いはず。
ここでは、電子契約について基本的な情報をお伝えします。
2023年12月11日2024年01月30日
そもそも、電子契約って何?
従来、企業間で商品やサービスの売買を行う際には紙の契約書で契約を交わしていました。紙の契約書に契約者同士が署名捺印することで双方の合意が成立したという証になるわけです。仮に契約後に契約不履行などのトラブルがあり、裁判になったとしても、契約書が証拠となります。
一方、電子契約は紙の代わりにパソコンで契約書のデータをやり取りして契約を結ぶやり方です!早速詳細を確認してみましょう!
紙の契約書との違い
| 電子契約 | 紙の契約書 | |
|---|---|---|
| 形式 | 電子データ | 紙に印字された書面 |
| 押印 | 電子署名 | 押印もしくはサイン |
| 印紙 | 不要 | 必要 |
| 送付方法 | インターネットによる送信 | 持参、もしくは郵送 |
| 保管先 | サーバー(主に自社・社外も含む) | 書棚、倉庫など |
| 法的証拠力 | 本人電子署名があれば効力あり | 効力あり |
紙の契約書の場合、契約が締結されるまでに「作成」「相手との受け渡し」などで時間も手間もかかりますが、電子契約の場合は手間がかからずスムーズ。また、物理的な保管場所も印紙も不要。経費を抑えることにもつながるため、ますます注目を集めています!
電子契約の法的効力(タイムスタンプとは)
とても便利な電子契約ですが、気になるのがその法的証拠力。
従来は、安全性のために紙の契約書に印鑑を押していましたが、電子契約では「電子署名」と「タイムスタンプ」という2つの機能によって安全性を保っています。
電子契約では押印する代わりに「電子署名」を付与して署名者本人が締結したことを証明します。さらに、「タイムスタンプ」を付与することで契約書が「いつ」締結されたかを記録されるため非改ざん性を担保します。
電子契約のメリット
経費の削減、業務の効率化などメリットが多数得られる電子契約。これから導入を検討されているご担当者のために、これらのメリットについて具体的に解説いたします。
01印紙税、郵送料などのコストを削減!
紙の契約書を締結する際には、印紙税がかかります。たとえば、「3千万円を超え5千万円以下は1万円」など、契約金額が大きくなればなるほど印紙税も増えていき、その他にも郵送代がかかります。
取引先が多い企業の場合、相当なコストがかかっているはずですが、電子契約にすれば、印紙税も郵送代も不要となるため、これらのコストを大幅に削減することができます。
02業務の効率化が実現!
紙の契約の場合、契約書作成から締結まで、そして契約締結後にも複数の細かい作業が必要であり業務フローが煩雑でした。しかし、電子契約にした場合、これら全ての作業をパソコンで完結させることができるため、楽に、そしてスムーズな流れで業務を行うことが可能となります。
作成、締結から保管・管理に至るまでの面倒な作業を簡略化できるので、作業スピードがアップし人件費の削減にもつながります。
03保管スペースが不要に
紙の契約書の場合、それらを保管しておくスペースが必要でした。しかし、電子契約の場合、自社のサーバー内、もしくは電子契約サービス会社を活用した場合は社外の安全なデータセンターなどに保管することができるため、これまで契約書の保管スペースとして使用されていた場所を別の目的で使用することができます。
04契約書の改ざんを防ぐことで、コンプライアンスを徹底強化
紙の契約書の場合、誰かが悪意を持って書面の内容を改ざん、偽造した場合、その事実を証明するためには多くの時間、労力、そして費用がかかります。
しかし、電子契約の場合は、万が一、誰かが改ざんしようとしたとしても、その事実が記録として残ります。また、その電子署名が本人のものであること、誰にも改ざんされていないことを証明することも可能。そもそもシステム上、権限を与えられた人しか署名をすることができない仕組みになっているため安心です。
このように、契約書の不正を防止する処置・対策をしっかりと取ることで、コンプライアンスの強化が実現できます。
電子契約のデメリット
電子契約にもデメリットがあるのは事実。その内容を把握・理解した上で自社の課題点を明確にして取り組むことが大切です。
01取引先に電子契約サービスへの加入依頼が必要
電子契約を実現するためには、利用する認定事業者、もしくは電子契約サービス会社のルールに基づき、契約を結ぶ相手である取引先にも電子契約サービスへの加入をお願いする必要があります。
認定事業者を利用する場合は、印鑑証明書、登記簿謄本などの公的証明書類の提出が必要であり、電子契約サービス会社を利用する際にはアカウントの登録が必要。また、事業者などによっては加入時・サービス利用時に費用が発生します。
02認定事業者を利用する場合は、電子証明書の取得が必要
認定事業者を使って電子署名を行う場合は、身分証明書ともいえる電子証明書を取得する必要があります。会社の従業員など個人のものが必要なため、申請する際には申請者本人から同意を得た上で手続きを行う必要があります。電子契約サービス会社独自のサービスを利用する場合は、簡単、スムーズに契約を締結することができます。
03税務調査に備え、電子帳簿保存法による運用が必要
電子契約の運用に関しては、電子帳簿保存法による定めがあり、規定に基づく運用管理体制で保存法を整備しておく必要があります。
具体的には、保存場所、保存期間、真実性要件(タイムスタンプ、もしくは「正当な理由のない訂正及び削除の防止に関する事務処理規程の制定、及び当該規定に沿った運用」のいずれか)、検索機能、説明書の備え付けに関する細かい取り決めに従い、運用します。
ご紹介したように、電子契約にはデメリットがありますが、オンラインショッピング、コンビニエンスストア、百貨店、不動産業者など導入したことで営業的にも多くの成功をおさめた企業は豊富。課題点を解決することで多くのメリットを手に入れ、成功をおさめています。
おすすめ電子契約3選
01操作が簡単で安い!クラウドコントラクト

中小企業や個人事業主向けの電子契約サービス。業界最安値クラスの導入しやすいお手頃価格と、操作が簡単ですぐに使いこなせるシンプルな機能が特徴です。
| 対象 | 月額料金 | プラン数 | お試し |
|---|---|---|---|
| 個人 法人 |
2,178円~ | 3個 | 無料 |
02高機能な有名サービスクラウドサイン

業界内で高い知名度を持つサービス。大手企業のニーズに答える豊富な機能をそろえています。
| 対象 | 月額料金 | プラン数 | お試し |
|---|---|---|---|
| 個人 法人 |
11,000円~ | 4個 | 無料 |
03カスタマイズ機能が豊富GMOサイン

オプション機能が豊富で、自社のニーズに合わせて機能をカスタマイズできるサービス。主に大企業向け。
| 対象 | 月額料金 | プラン数 | お試し |
|---|---|---|---|
| 個人 法人 |
8,800円~ | 4個 | 無料 |