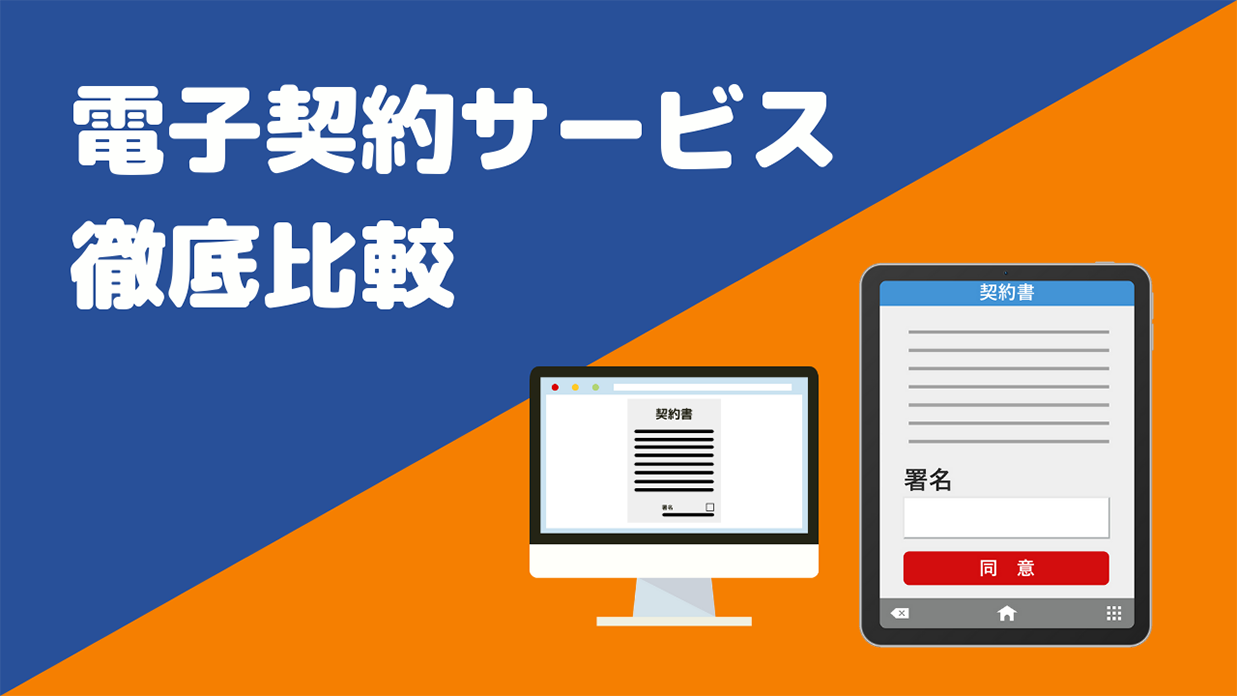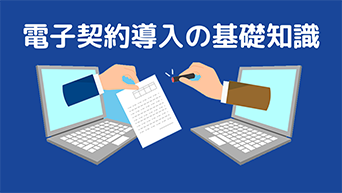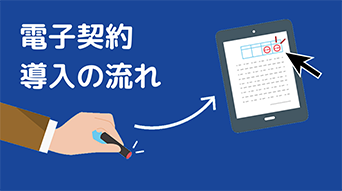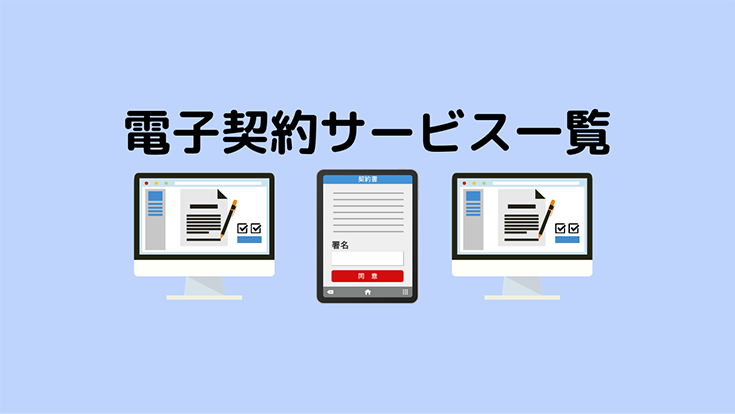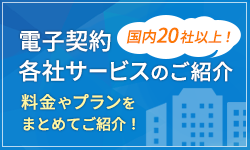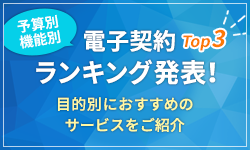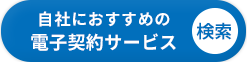2025年10月28日2025年11月27日
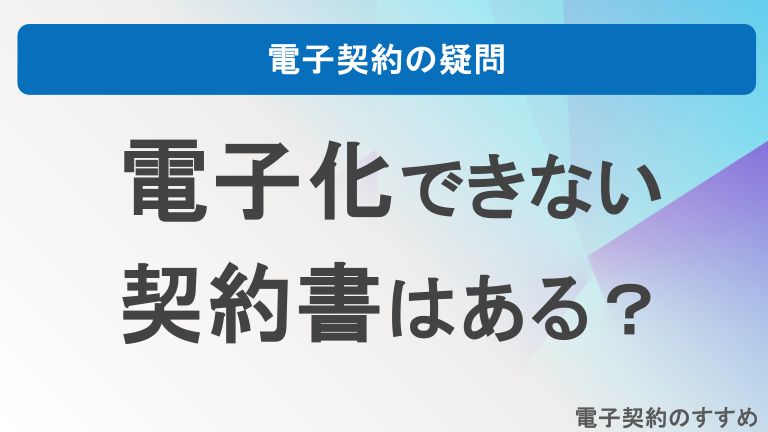
電子契約の導入を検討しているものの、「自社で使っている契約書が電子契約できるものなのか」、「電子契約できない契約書はあるのか」など、不安や疑問を抱える方も多いのではないでしょうか。この記事では、電子契約できない契約書の具体例や、電子化の可否を見分けるためのポイントから、電子契約導入方法を解説します。
電子化できない契約はある?
原則として、ほとんどの契約は、電子契約で締結することが可能ですが、法律によって書面(紙)での作成や交付が義務付けられている一部の文書では、現在でも電子契約ができない、または相手方の承諾や希望、請求が必要となります。
電子契約できない契約書を電子契約で締結してしまったり、相手方の承諾のないまま電子契約を強行してしまうと、後に問題となってしまうこともあるため、電子契約できない契約書は、事前に把握しておくことをおすすめします。
電子契約できない契約一覧
電子契約ができないのは、主に以下の契約です。
| 文書名 | 主な根拠法令 |
|---|---|
| 事業用定期借地契約 | 借地借家法23条 |
| 企業担保権の設定又は変更を目的とする契約 | 企業担保法3条 |
| 任意後見契約 | 任意後見契約に関する法律3条 |
| 農地または採草放牧地の賃貸借契約 | 農地法21条 |
上記の契約書では、公正証書での作成が必須であったり、法律により書面での作成・交付が義務付けられているため、電子契約や電子での交付ができないものとなっています。
相手方の承諾を得れば電子契約・電子交付が可能な文書
文書を電子契約や電子交付する際、相手方の承諾・希望・が必要となるのは、主に以下の文書です。
| 相手方のアクション | 文書名 | 主な根拠法令 |
|---|---|---|
| 承諾 | 事業者が交付する申込書・契約書・概要書 | 改正特商法4条・13条・第18条・20条 |
| 承諾 | 下請事業者へ交付する「給付の内容等」の記載書面 | 下請法3条 |
| 承諾 | 建設工事請負契約書 | 建設業法19条、建設業法施行規則13条 |
| 承諾 | 設計受託契約の重要事項説明書 | 建築士法24条 |
| 承諾 | 工事監理受託契約の重要事項説明書 | 建築士法24条 |
| 承諾 | 定期建物賃貸借契約の説明書 | 借地借家法38条 |
| 承諾 | 宅地建物の売買・交換の媒介契約書 | 宅建業法34条 |
| 承諾 | 宅地建物の売買・交換の代理契約書 | 宅建業法34条 |
| 承諾 | 宅地建物の売買・交換・賃借の重要事項説明書 | 宅建業法35条 |
| 承諾 | 宅地建物取引業者の交付書面 | 宅建業法37条 |
| 承諾 | 不動産特定共同事業契約書面 | 不動産特定共同事業法24条、25条 |
| 承諾 | 投資信託契約約款 | 投資信託及び投資法人に関する法律5条 |
| 承諾 | 貸金業者が交付する契約締結前交付書面 | 貸金業法16条 |
| 承諾 | 貸金業者が交付する生命保険契約等に係る同意前の交付書面 | 貸金業法16条 |
| 承諾 | 貸金業者が交付する契約締結時交付書面 | 貸金業法17条 |
| 承諾 | 貸金業者が交付する受取証書 | 貸金業法18条 |
| 承諾 | 割賦販売契約の契約書面 | 割賦販売法4条・35条 |
| 承諾 | 旅行契約の説明書面 | 旅行業法12条、旅行業法施行令1条等 |
| 希望 | 労働条件通知書 | 労働基準法15条、労働基準法施行規則5条 |
| 希望 | 派遣元企業が派遣労働者へ交付する就業条件明示書 | 労働者派遣法34条、労働者派遣法施行規則26条 |
| 請求 | 金銭支払の受取証書 | 民法486条 |
これらの文書の多くは、以前までは「書面での交付」が義務付けられていましたが、近年の法改正により、「相手方の承諾・希望・請求」を条件として電子化が解禁さたものとなっています。
電子契約できるかどうかの見分け方
電子契約ができるかどうかを見分けるポイントは、法律によって「書面や公正証書の作成の義務」があるか、「書面交付が必須」とされていないかという点です。
また、その契約が、契約当事者の力関係・パワーバランス・情報格差に著しい有利不利が生じる可能性がある場合には、電子化に相手方の承諾や希望が必要となるケースが多くなっています。
【電子化の可否確認ポイント】
契約の種類を確認する
法律で公正証書や書面交付の義務付けがある契約でないか確認しましょう。
相手方の承諾が必要な契約でないか確認する
該当する場合は、相手方から電子化の承諾や希望を得られれば電子契約が可能です。
電子契約できる代表的な契約書の一覧
以下は条件なしで電子契約できる代表的な契約書の一覧です。
| 契約書名 |
|---|
| 取引基本契約書 |
| 売買契約書 |
| 業務委託契約書 |
| 秘密保持契約書 |
| 一般的な請負契約書(※建設業法19条3項を除く) |
| 一般的な発注書・発注請書(※下請法3条2項を除く) |
| 雇用契約書 |
| 賃貸借契約書 |
| 代理店契約書 |
| 保証契約書 |
| サービス利用契約書 |
| 誓約書 |
| 顧問契約書 |
契約書の電子化に関連する主な法律
電子契約を行う場合は、契約書の電子化に関する法律を把握しておくことが大切です。
契約書の電子化(電子契約の締結および保存)に関連する主な法律は、大きく分類すると「有効性を担保する法律」「保存に関する法律」「電子化の規制や緩和に関する法律」の3つとなります。
1. 有効性を担保する法律
電子契約が紙の契約書と同等の法的効力を持つための根拠となる法律です。これは電子契約の根幹となるため、必ず確認しましょう。
【電子署名及び認証業務に関する法律(電子署名法)】
電子署名法では、電子契約が法的に有効な証拠力を保つためのルールが定められており、電子契約の有効性の根幹となる法律です。特定の要件を満たした電子署名が付された電子文書は、紙の契約書への押印や署名と同様に「真正に成立したもの(本人の意思に基づいて作成されたもの)」と推定されることを定めています(第三条)。
【民法】
法令で書面が義務付けられていない限り、電子契約でも有効に契約が成立することの一般的な根拠となっています。法令で書面での契約が義務づけられていない限り、契約の成立に書面は必須ではないことを示しています。(民法第522条2項)
【民事訴訟法】
電子署名法と合わせて、電子契約書が紙の文書と同様に高い証拠力を有するための法的基盤となります。 裁判で電子契約書が証拠として認められるためのルールに関わります。
2. 契約書や取引データの保存に関する法律
電子化された契約書や取引データを、企業が保存するためのルールを定めた法律です。
【電子帳簿保存法(電帳法)】
電子帳簿保存法は、国税関係帳簿書類(契約書、領収書、請求書など)を電子データで保存する際の要件を定めた法律です。電子取引(電子契約サービスやメールなどで授受したデータ)で受け取った契約書は、原則として電子データのまま保存することが義務付けられています(2024年1月以降)。真実性(タイムスタンプ、訂正削除履歴など)や可視性(検索機能など)の確保が求められます。
【e-文書法】(民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律)
e-文書法は、法律で保存が義務付けられている文書について、紙ではなく電子データ(電磁的記録)による保存を広く認める法律で、電子帳簿保存法より対象範囲が広く、様々な分野の文書の電子保存を認める根拠となっています。
3. 契約書の電子化の規制や緩和に関する法律
以下は、特定の分野の契約について、電子化の可否や条件を定めた法律です。
【IT書面一括法】
特定の法令で義務付けられている「書面による交付」について、相手方の承諾があれば電子的な方法(メール、PDFなど)で交付することを認める法律の総称です。これにより、消費者保護の観点から書面交付が必須とされていた多くの分野(例:特定商取引法、金融関連法)で、電子化が可能になりました。
【宅地建物取引業法】
不動産取引における契約書や重要事項説明書(35条書面、37条書面)について、2022年の法改正により、当事者の同意を得ることで電子化(IT重説や電子契約)が可能になりました。
【建設業法】
建設工事の請負契約書などについて、相手方の承諾があれば電子契約が認められています。
【印紙税法】
紙の契約書に課税される印紙税について定めた法律です。電子契約書は「課税文書」にあたらないという政府見解に基づき、印紙税が非課税となります。これは電子契約の大きなメリットの一つです。
これらの法律を理解することで、安心して電子契約の導入と運用を進めることができます。
契約書を電子化するメリット
契約書を電子化する一番のメリットは、コスト削減です。
印刷・保管・郵送・用紙代など、契約書の発行~締結までの様々なコストをカットすることができ、印紙税も0円となるため、導入する電子契約によっては大幅なコスト削減が叶います。
また、紙の契約では、印刷や製本、押印、郵送などアナログな作業が伴いますが、電子契約では電子データで送付するため、契約業務の時間削減となり、業務効率の改善にも繋がります。
以下記事で、電子契約のメリットデメリットを解説していますので、よろしければぜひご参考下さい。
電子契約の導入方法
電子契約を導入するには、いくつかの方法がありますが、手軽に導入する場合は、「電子契約サービス」の利用がおすすめです。
導入方法1:電子契約サービス(クラウドサービス)を利用する
契約書の作成・署名・管理まで一連のプロセスを、クラウド上で安全かつ効率的に行うための専門サービスを利用する方法です。現在、最も主流の方法です。
基本的に、契約書の送付~締結・保管の機能と、法的に必要となる電子署名やタイムスタンプの付与機能が標準搭載されているため、簡単に導入することができる点が魅力です。
サービスにより機能や価格が異なるため、自社のニーズに合わせて選ぶ必要があります。
以下記事ではニーズ別に電子契約サービスを紹介していますのでぜひご参考下さい!
導入方法2:メールや文書作成ソフトを活用する
紙を使わず、電子データ(WordやPDFファイル)をメールでやりとりしたものも電子契約となります。この方法は簡単ではありますが、タイムスタンプや電子署名の付与は自社で行わなければならない為、電子署名法上の要件を完全に満たすには専門知識が必要となります。
以下記事では、無料で電子署名を行う方法をご紹介していますのでぜひご参考下さい。
導入方法3:システムを自社開発または外部委託する
自社ようの電子契約システムを独自に開発することで、電子契約の導入が叶います。自社の特殊な業務フローや既存システムとの連携を優先したい場合にはこの形が理想となりますが、開発コストやシステムの完成・導入までは多くの時間を要します。
まとめ
現在は、一般的な契約であれば、ほとんどの契約書を電子契約で締結することが可能です。
電子契約できない契約については、法律によって「書面や公正証書の作成の義務」や「書面交付が必須」とされているものとなり、相手方の承諾や希望が必要となるケースとしては、契約当事者の力関係・パワーバランス・情報格差に著しい有利不利が生じる可能性がある場合となるため、この点を覚えておきましょう。
電子契約の導入は、自社独自の電子契約システムが欲しい場合以外は、簡単に導入できる電子契約サービスを活用がおすすめです。無料プランや無料トライアルが利用可能なサービスもあるため、ぜひチェックしてみてください。
おすすめ電子契約3選
01操作が簡単で安い!クラウドコントラクト

中小企業や個人事業主向けの電子契約サービス。業界最安値クラスの導入しやすいお手頃価格と、操作が簡単ですぐに使いこなせるシンプルな機能が特徴です。
| 対象 | 月額料金 | プラン数 | お試し |
|---|---|---|---|
| 個人 法人 |
2,178円~ | 3個 | 無料 |
02高機能な有名サービスクラウドサイン

業界内で高い知名度を持つサービス。大手企業のニーズに答える豊富な機能をそろえています。
| 対象 | 月額料金 | プラン数 | お試し |
|---|---|---|---|
| 個人 法人 |
11,000円~ | 4個 | 無料 |
03カスタマイズ機能が豊富GMOサイン

オプション機能が豊富で、自社のニーズに合わせて機能をカスタマイズできるサービス。主に大企業向け。
| 対象 | 月額料金 | プラン数 | お試し |
|---|---|---|---|
| 個人 法人 |
8,800円~ | 4個 | 無料 |