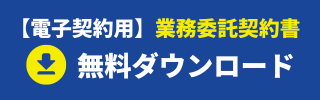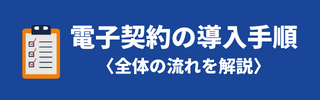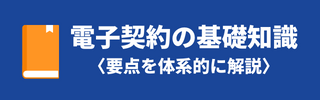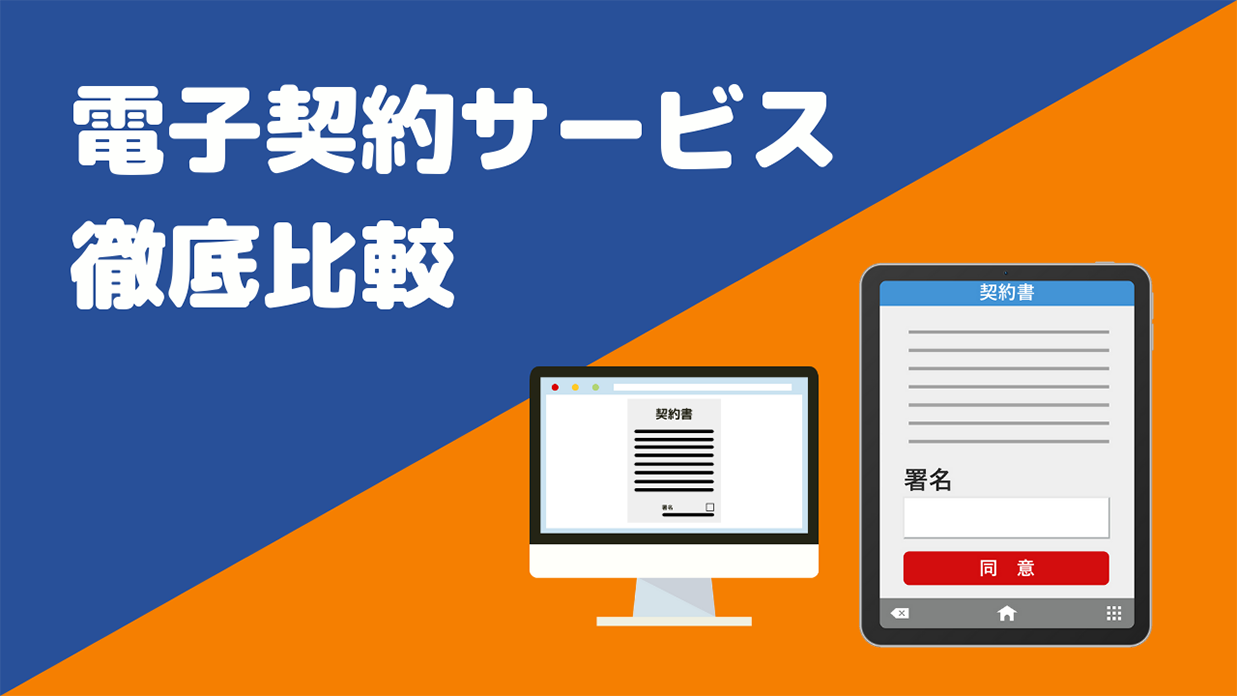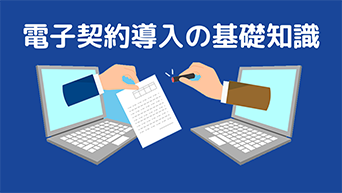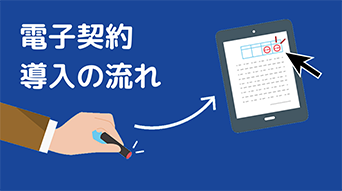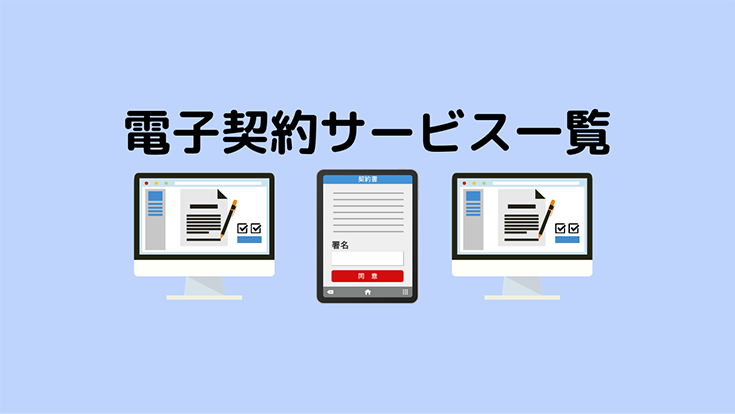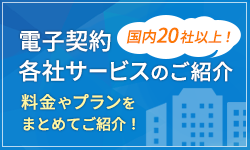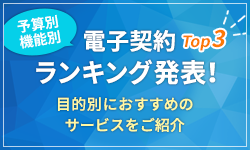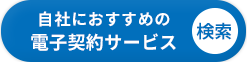2024年06月27日2024年06月27日
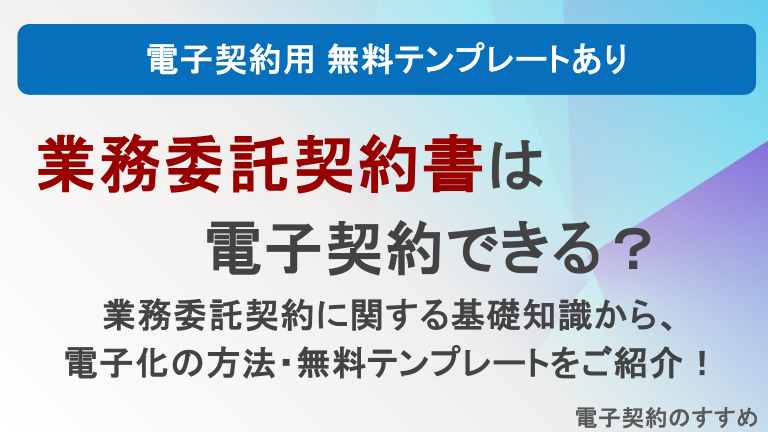
業務委託契約とは
業務委託契約とは、本来、自社で行う業務を外部の企業や個人に依頼する際の契約です。
民法では、請負契約もしくは委任・準委任契約(643条、656条)、請負契約(632条)のいずれかに分類されます。
業務委託契約は、他の一般的な契約と同様に、成果物や業務について当事者同士が契約内容を了承していれば、契約書の取り交わしは必須ではありません。
しかし口頭のみだと、「言った」「言わない」のトラブルに繋がる恐れがあるため、発注者も受注者も、安心して取り引きができるよう、委託業務の内容や権利、再委託の可否やルール、報酬額、支払いの条件などを明記した業務委託契約書を締結することが推奨されます。
業務委託契約の種類
業務委託契約は、依頼する業務の内容や成果物に対する責任の有無などにより、請負契約・委任契約・準委任契約の3つに分かれます。
請負契約
請負契約は、成果物の完成を目的とした契約です。たとえば、アプリケーションの完成、動画の納品、Webサイトの記事執筆などが該当します。受託者は成果物を完成させる義務があり、その成果に対して注文者から報酬が支払われます。成果が不十分だった際には、やり直しや損害賠償の対象となることもあります。IT関連だけでなく、建設等の工事や運送、物品の加工など幅広く用いられます。
委任契約
「法律行為」を伴う業務の「遂行」を目的とする契約です。成果物の完成は目的としていません。また、ここでの法律行為とは、当事者間の意思表示によって権利や義務の移行・取得などを発生させる行為で、大まかに言えば、仕業に依頼する法律に関する手続きです。弁護士への訴訟依頼、税理士に税務申告を依頼することなどが挙げられます。受任者は誠実に遂行する義務を負うという善管注意義務があります。
準委任契約
法律行為ではない事務処理や技術的サービスの業務の遂行を目的とする契約です。コンサルティング業務、SEの客先常駐、家庭教師、ビルの清掃業務、警備業務など継続的なサービス提供や業務遂行自体が目的となるもので幅広く用いられます。委任契約と同様、善管注意義務がありますが、民法に規定されておらず、クライアントの指揮命令に属するわけでもないことから、雇用契約とも異なります。
業務委託契約の報酬の支払い方法
業務委託契約における報酬の支払い方法は主に3種類に分類されます。
定額報酬制
定額報酬制は、契約期間や業務内容に応じて、毎月一定額の報酬を支払う方式です。「1ヶ月につき〇万円」など、特定の単位に基づきます。業務の成果物が明確でない場合や、継続的な支援・作業が求められるケースに適しています。
たとえば、弁護士や税理士などの専門家が顧問契約、システムの保守運用、コンサルティングなどが該当します。
成果報酬制
成果報酬制は、一定の成果が得られた場合にのみ報酬を支払う方式です。たとえば、売上向上、集客数、契約獲得数などの「成果指標(KPI)」を事前に合意し、それに応じて報酬が変動します。営業代行や店舗運営の委託、広告運用などで用いられます。成果報酬型の場合、「売上に対して〇%」等として成果へのコミットメントに応じた報酬が定められます。
単発報酬制
単発報酬制は、特定の業務・作業単位に対して、その都度報酬を支払う方式です。単発のタスク、短期業務、明確な成果物がある案件などに適しています。この方式は、請負契約の性質が強く、明確な完了点がある業務にとても合致しています。デザイン制作や動画納品、原稿の執筆などで用いられます。「ライティング1記事(4000字)につき〇円」のような形です。
業務委託契約書に記載すべき内容
業務委託契約とは、特定の業務を企業や個人事業主などの外部パートナーに依頼する際に取り交わされる、大切な契約文書です。後々のトラブルを回避し、スムーズな業務運営を実現するためには、以下の各条項を明確に盛り込むことが非常に重要です。
以下で、業務委託契約書の条項例をご紹介します。
業務委託契約書の条項例
①委託業務の内容
委託する業務の具体的な内容や範囲を明記する項目です。納品物がある場合は、その種類・数量・仕様なども具体的に記載し、双方の認識違いによるトラブルを防止します。
②委託期間
契約が有効となる期間を定めるもので、開始日と終了日を明確に設定します。契約の自動更新の有無についても、あらかじめ取り決めておくと安心です。
③報酬額と支払い時期・支払方法
報酬の金額と支払いに関するルールを定める重要な項目です。金額は明確に記載し、未確定の場合は計算式を示します。税込・税別や振込手数料の負担者、支払い遅延時の遅延損害金なども忘れず記載しましょう。
④業務担当者
業務を実際に担当する人物を指定する場合の条項です。特定のスキルを持った担当者が必要な業務では、誰が従事するかを明確にしましょう。また、企業など複数名が仕事に従事している場合は特に重要です。
⑤再委託
受託者が第三者へ再度業務を委託(再委託)する場合の条件を規定します。無断での再委託を防ぐため、許可制とする、範囲を限定するなどの取り決めが必要です。
⑥権利の帰属
納品物に関連する著作権や知的財産権の帰属先を定めます。通常は委託元に帰属させる形が多いため、契約にその旨を明記します。著作者人格権の不行使条項もセットで記載するのが一般的です。
⑦秘密保持
機密情報や個人情報を保護するための条項です。秘密情報の定義を明確にし、開示範囲や保管方法なども含めて取り決めておくと実務上有効です。
⑧報告義務
業務の進捗状況や問題点の報告を義務づける内容です。定期報告の有無、報告頻度、想定外のトラブル発生時の連絡ルールなども盛り込まれます。
⑨禁止事項
業務実施中に行ってはならない行為について定める条項です。不正行為や競業行為など、あらかじめ防止したいトラブルを想定して記載することで、円滑な運営に役立ちます。
⑩損害賠償
契約違反や過失により相手方に損害が発生した場合の補償に関する条項です。ただし、発注側に一方的に有利な内容は下請法などの法令に抵触するおそれがあるため、公平性が求められます。
⑪解約(契約解除)
契約を途中で終了する際の条件を定めます。通知期限や解除理由の明確化に加え、中途解約時の報酬支払いルールなども、事前に取り決めておくことが大切です。
業務委託契約は電子契約できる?
業務委託契約は、書面(紙)の発行が義務とはされていないため、事前に電子契約で業務委託契約書の取り交しを行うことについて双方で了承していれば、電子契約を行うことが可能です。
近年は、委託業務もオンライン対応が多くなっているので、業務委託契約を電子契約で行うことは、業務効率の改善に繋がるのではないでしょうか。
また、電子契約では印紙税がかからないため、収入印紙も不要となり、時間・コストの両面が削減できるため双方へのメリットも大きいものとなります。
業務委託契約書を電子契約用に変更する方法
業務委託契約書は、書面契約と電子契約で、大幅に契約書の内容を変更する必要はないため、基本的には現在使用している契約書の内容で「書面」と記載がある箇所を微調整すれば、使用することができます。
変更例は以下をご参考下さい。
変更例
「書面による承諾」等の記載がある箇所の文言を変更
例:書面:書面による承諾が無い限り
電子契約:書面または双方が合意した電磁的措置による承諾が無い限り
末尾文言(本契約の成立の証として、以降)を変更
例:書面:本書2通を作成し、各自記名押印の上、各1通ずつ保有する。
電子契約:本電子契約書ファイルを作成し、それぞれが電子署名を行う。
なお、本契約においては、電子データである本電子契約書ファイルを原本とし、同ファイルを印刷した文書はその写しとする。
押印欄を削除(任意)
電子契約では、押印・捺印は不要となるため、電子契約サービスを使用する場合には書面から、押印・捺印の箇所は削除しても問題ありません。
※電子契約では、ハンコの有無は特に法的な効力はなく、締結時に付与される電子署名・タイムスタンプが書面契約におけるハンコの役割を担います。
【電子契約用】業務委託契約書 無料テンプレートのご紹介
さて、ここまで、業務委託契約書について、電子化のメリットや方法をご紹介しましたが、いかがでしたでしょうか?
既に自社の業務委託契約書がある方は、書類の内容を少し調整するだけで簡単に電子契約で使用できますので、当記事をお役立ていただければ幸いです。
これから自社用の業務委託契約書を作成をされる方も、ご安心下さい!
当サイトでは、電子契約用に調整した契約書テンプレートをご用意しておりますので、ぜひご活用頂ければ幸いです。
※上記ファイルは、あくまでも電子契約用に調整した契約書のサンプルとなりますので、ご利用については弊社では責任を負いかねます。必ず専門家へご相談頂き、内容を自社用に変更・カスタマイズした上でご使用下さい。
業務委託契約書のよくある質問
業務委託契約書は、いつ・だれが作る?
通常は委託側(発注者側)が業務を開始する前、または具体的な条件が固まった段階で作成するのが一般的です。
ただし、受託者(受注者側)が作成しても法律上問題なく、業務委託契約書の場合、契約の重要性を考慮し、利益を最大化したい側が主導して作成するほうが有利に動けます。
業務委託契約書には印紙が必要?
業務委託契約書は、多くの場合は印紙が不要です。
継続的な事務処理などを依頼する「委任契約」や「準委任契約」の場合は、原則として印紙は不要です。
その内容が「請負契約」に該当する場合、収入印紙が必要になります。
業務委託契約書は電子契約できる?
はい、可能です。業務委託契約書に関しては書面の発行が法律でそもそも義務付けられていないため、オンライン上で行う電子契約においても問題なく行えることになります。
業務委託契約は雇用契約とどう違うの?
様々違いはありますが、大前提、労働基準法が雇用契約には適用されるのに対して業務委託契約には適用されません。そのため、業務委託契約には指揮命令権がなく、働き方は個人の裁量に任されます。だからこそ、業務委託は、多くの場合、仕事の完成や成果物の納品に対し報酬が支払われるようになっています。
委託者(発注者側)が契約書を作成する時のポイントは?
委託者側が作成する際は、依頼したい業務内容と成果物を具体的に明記することが最重要です。また、報酬額や支払い条件、納期、検収基準、秘密保持義務、損害賠償、契約解除の条件なども詳細に定めることにより、後のトラブルを未然に防げます。重要なのは、契約書作成により曖昧さをなくすことです。
受託者(受注者側)が契約書を作成する時のポイントは?
受託者側が作成する際は、自身の業務内容など、業務遂行上の重要な項目が明確に定められているかを確認しましょう。また、無理のない納期設定、報酬額と支払い条件、作業途中の追加費用や変更への対応、成果物の著作権の帰属、そして自身の責任範囲を具体的に記載することも重要になります。
収入印紙は委託者と受託者どちらが負担する?
業務委託契約において、印紙を委託者、受託者のどちらが負担するがは決まっておらず、契約書を作成した側が負担する(印紙を貼る)のが原則になっています。ただし、当事者間の合意があれば、折半や、申し出たいずれか一方が負担することも可能です。契約前に取り決めておくとスムーズです。
システム開発の業務委託契約書はどちらが作成することが多い?
システム開発においては、案件の中身や相手方との力の均衡より、発注者が契約条件を定めて契約書を用意することが一般的ですが、
企業と個人主・フリーランスの契約が増えている現在では、契約不適合責任やシステムの仕様、費用面の対応など、リスク対応を明確にしたいという観点から、受託者側が契約書を提示するケースも増えています。
製造や加工に関する委託ではどちらが契約書を作成することが多い?
製造や加工に関する委託の場合、下請法の対象となる場合が多いため、委託者(発注者側)が契約書を作成することが多くなっています。これは、下請法で発注者に契約書交付義務があるためです。
コンサル業務関連の委託ではどちらが契約書を作成することが多い?
コンサル関連の業務委託契約では、自社サービスの提供条件を明確にさせるために、受託者(受注者側)となるコンサルタントが契約書を作成するケースが多くなっています。また、継続的でない単発のコンサル関連案件でもこのような場合が多くなります。
Web制作関連の委託では、どちらが契約書を作成することが多い?
Web制作関連業務では、制作会社が受託者側となるため、制作会社が契約書を作成するケースが多くなっています。しかし、発注者が大手制作企業の場合は、発注者側で用意された契約書を使用するパターンもあります。
業務委託契約がない場合に想定されるリスクは?
契約書がないと、業務内容や報酬が聞いていた話と違ったときに泣き寝入りせざるを得ない、もしくは損害賠償請求という大きなトラブルにまで発展してしまう可能性があります。
電子契約サービスの選び方
電子契約をこれから選ぶ方は以下ページもぜひご覧ください!
おすすめ電子契約3選
01操作が簡単で安い!クラウドコントラクト

中小企業や個人事業主向けの電子契約サービス。業界最安値クラスの導入しやすいお手頃価格と、操作が簡単ですぐに使いこなせるシンプルな機能が特徴です。
| 対象 | 月額料金 | プラン数 | お試し |
|---|---|---|---|
| 個人 法人 |
2,178円~ | 3個 | 無料 |
02高機能な有名サービスクラウドサイン

業界内で高い知名度を持つサービス。大手企業のニーズに答える豊富な機能をそろえています。
| 対象 | 月額料金 | プラン数 | お試し |
|---|---|---|---|
| 個人 法人 |
11,000円~ | 4個 | 無料 |
03カスタマイズ機能が豊富GMOサイン

オプション機能が豊富で、自社のニーズに合わせて機能をカスタマイズできるサービス。主に大企業向け。
| 対象 | 月額料金 | プラン数 | お試し |
|---|---|---|---|
| 個人 法人 |
8,800円~ | 4個 | 無料 |