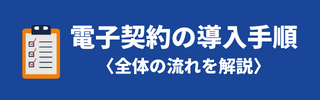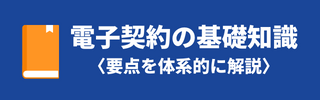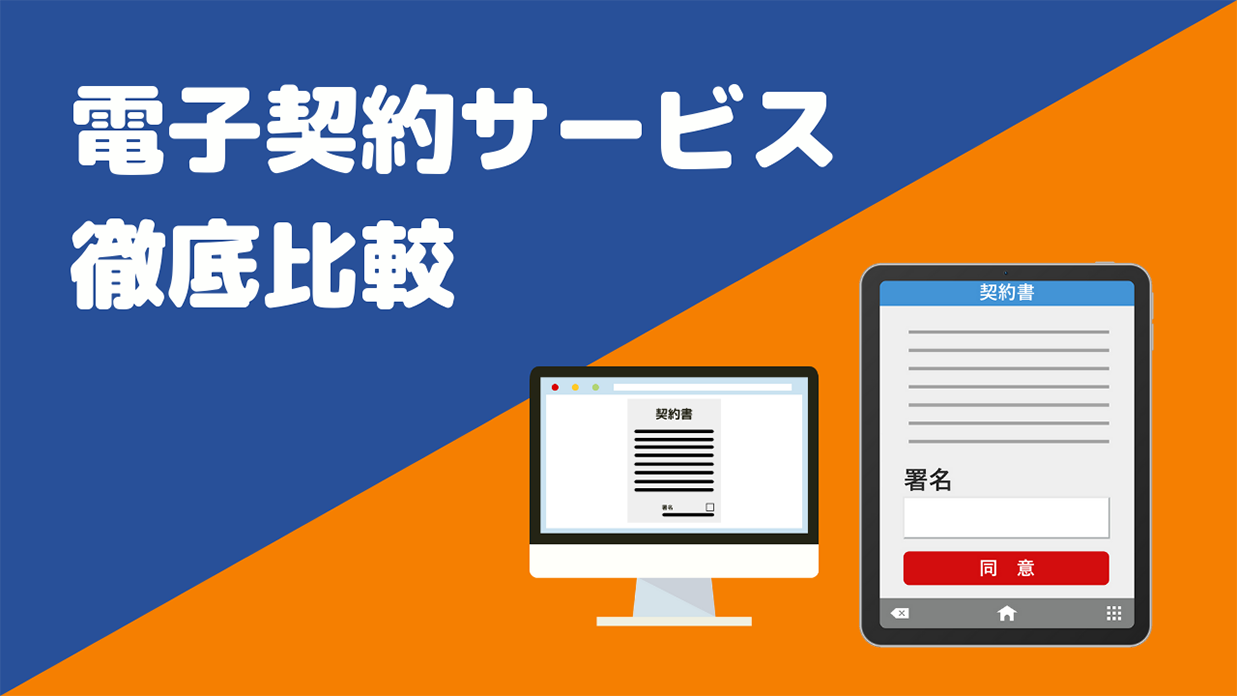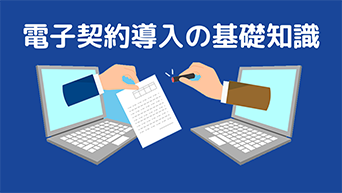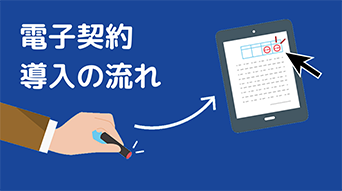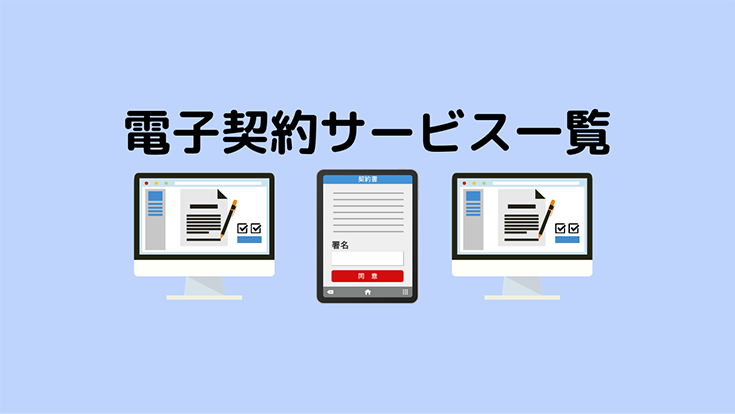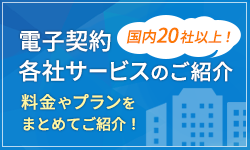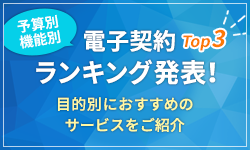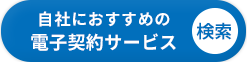2025年03月31日2025年03月31日
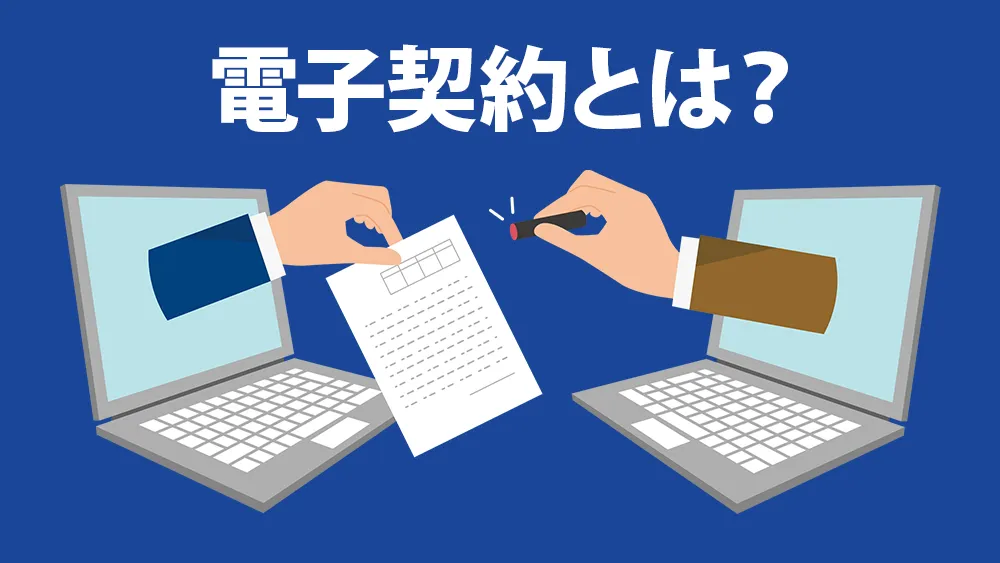
かつて契約書は、紙の書類に押印したものが基本でした。しかし2001年には「電子署名法」という電子契約につながる法律が施行されました。その後も、2001年に「IT書面一括法」、2005年に「e-文書法」が施行されたほか、1998年に施行されて以降、相次いで改正された「電子帳簿保存法」、2021年に施行された「デジタル社会形成整備法」によりペーパーレス化が推進され、現在では企業が取り交わす殆どの契約書は電子契約できるようになっています。
このような電子契約は、効率性や経済性、安全性を持つ方法として、紙の契約書に代わり、日本社会でも普及しつつあります。
電子契約とは?基礎知識をわかりやすく解説
電子契約とは、インターネット上でデジタル技術を利用して、電子ファイルに電子データを記録して締結する契約のことを言います。押印の代わりに電子署名を、印鑑証明書の代わりに電子証明書を、契印・割印の代わりにタイムスタンプなどを利用することで、紙による契約書と同等の法的効力を持たせています。
なお、電子契約を導入することにより、以下のような多くのメリットを得られます。
- ・契約書作成や契約に関するやり取りのコスト削減
- ・印紙税や事務経費、事務労力などのコスト削減
- ・契約書の保管や管理の効率化
- ・契約締結までの時間短縮
- ・類似契約書の作成業務の効率化
- ・リモートワーク対応への容易化
- ・契約更新時の確認漏れの防止
- ・コンプライアンスの強化
電子契約の法律的な定義とは
電子契約は、「電子委任状法」の法律によって以下のように定義されています。
2 この法律において「電子契約」とは、事業者が一方の当事者となる契約であって、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により契約書に代わる電磁的記録が作成されるものをいう。
電子委任状法(電子委任状の普及の促進に関する法律)
「電子委任状法」は、正式には「電子委任状の普及の促進に関する法律」という名称で、電子委任状の普及促進や、電子契約や経済活動における電子取引や電子契約推進を目的とした法律で、2019年に施行されました。
電子委任状の普及促進のための基本的な指針や、電子委任状取扱業務の認定の制度に関して定められています。
「電子委任状法」で定めている電子委任状とは、委任状を単に電子データ化しただけではなく、権限範囲や委任期間などをネットワーク上で証明するものです。「電子委任状法」とは一般的な呼び方であり、正式には「電子委任状の普及の促進に関する法律」という名称があります。
電子契約の概要と仕組み
紙の契約書では、手書きの署名や押印をすることで、本人の意思で作成された契約書だと見なされますが、電子契約では、手書きによる署名や押印はできませんので、電子署名や、電子認証局の活用、メール認証などで契約者の本人性を証明します。
電子契約では、万が一トラブルが生じた際には、本人性の他、契約書が締結後に改ざんされていないことを証明する必要があるため、電子署名とあわせて、契約書の改ざん防止のために、契約書の内容と締結時刻を記録できるタイムスタンプがあると安心です。
従来の書面契約との違いと特徴
電子契約も紙の書面による契約も、契約を取り交わすために利用されるものです。電子契約書も法的効力のある契約書ではありますが、締結の方法などの共通点は多くはなく、別の物だと言えます。
書面契約と電子契約の主な違いは、以下の表をご確認ください。
| 書面契約 | 電子契約 | |
|---|---|---|
| 様式 | 紙 | 電子データ、PDF |
| 押印方法 | 押印 | 電子署名 |
| 本人性の証明方法 | 印鑑証明書 | 電子証明書 ※電子サインの場合は不要 |
| 改ざん防止方法 | 契印、割印 | タイムスタンプ |
| プリントアウト | 要 | 不要 |
| 保管場所 | 書庫、書棚、金庫など | サーバ |
| 送付方法 | 郵送、手渡し | ネット送信 |
| 印紙 | 要 | 不要 |
電子契約の基本的な流れとやり方
電子契約は、どのような手順でどのように行えばいいのでしょうか。ここからは、電子契約の基本的な流れと実際のやり方についてご紹介していきます。
電子契約を締結するにあたり、以下をチェックしておくことが求められます。これまで定められた電子契約に関する法律はもちろんのこと、契約である以上、さまざまな方面の法律や法令に目を通しておく必要があります。
【電子契約に関連する法律】
- ・電子帳簿保存法
- ・電子署名法
- ・IT書面一括法
- ・e-文書法
- ・デジタル社会形成整備法
【契約内容や契約手続きに関わる法律、法令】
- ・民法
- ・民事訴訟法
- ・建設業法・下請法
- ・宅地建物取引業法・借地借家法
- ・労働基準法
- ・特定商取引法
- ・電子消費者契約法(電子契約法)
- ・印紙税法
【より詳しく知りたい方は、以下の記事へ】
【押さえておきたい!】電子契約と電子署名に関する主な法律をご紹介!
契約締結までの具体的な手順
電子契約サービスによる契約締結の方法は、以下のような流れになります。
①アカウント登録
電子契約サービスのアカウントを登録する。
②契約書作成・アップロード
電子契約書を作成し電子契約サービスにアップロードを行う。
③契約書の送信・電子署名
電子署名を付与した電子契約書を送信する。
④契約締結
電子契約書の送信先と契約を締結する。
⑤契約書の保管
電子契約データは7年間の保存義務が課せられているので、電子契約締結後もその間、電子契約書データを保管しておく。
電子契約導入後の保管・管理方法
「電子帳簿保存法」に従い、電子契約書は以下の保存・保管方法を遵守する必要があります。
- ・紙にプリントするのではなく、電子データのまま保存しておく。
- ・定めた保管期間と保存場所を守る。
- ・過去の電子契約書を廃棄するのではなく、検索可能にしておく。
- ・見読性を確保しておく。
- ・タイムスタンプを付与しておく。
- ・電子契約書保存に関するマニュアルを準備しておく。
- ・セキュリティ対策を講じておく。
電子契約の主な種類と選び方
電子契約に必要となる電子契約サービスは多種多様です。そのため、自社に合ったサービスを選ぶには、主要なシステムの分類を把握し、契約の目的を明確にしておくことが大切です。ここからは、電子契約サービスの主な種類と選び方をご紹介します。
「当事者署名型(当事者型)」と「事業者署名型(立会人型)」の違い
| 当事者署名型 | 事業者署名型 | |
|---|---|---|
| メリット | ・送信者の電子証明書によって証拠力を高められる ・電子証明書による本人性が高いことで、なりすましのリスクが低い |
・電子証明書発行のための手間やコストが必要ない ・メールアドレスさえあれば電子契約を締結できる |
| デメリット | ・事前に電子証明書を取得する手間やコストが発生 ・電子証明書の有効期限(2〜3年程度)が到来するたびに更新手続きをする必要がある |
・「当事者署名型」より、なりすましのリスクは比較的高くなる ・「当事者署名型」より、法的効力を得にくい |
電子契約には「当事者署名型(当事者型)」と「事業者署名型(立会人型)」という2つのタイプがあります。
「当事者署名型(当事者型)」は、電子証明書の取得や管理、送信者と受信者とでの電子署名の付与や、認証局への申請など、より多くの手順が必要となります。
変わって「事業者署名型(立会人型)」は、電子契約サービスが電子署名を行い、メールアドレスさえあれば、電子契約を締結できるため手軽でコストがかからないものの、「当事者署名型」より若干法的効力は弱くなります。
タイプごとにそれぞれ、メリット・デメリットが存在します。
【より詳しく知りたい方は、以下の記事へ】
「立会人型」の電子署名は法的に有効!「当事者型」との違いも解説
クラウド型電子契約システムの特徴
電子契約書の作成・署名・保管・管理といった契約に関わる一連のプロセスをクラウド上で全て行う仕組みの電子契約サービスに、クラウド型電子契約システムがあります。
コスト削減ができるなど、多くのメリットを持つクラウド型電子契約システムは様々なサービスが存在していますので、以下のポイントに着目しながら選ぶ必要があります。
- ・自社の利用用途に、そのクラウドシステムが合致しているかどうか
- ・タイムスタンプなど、法的効力を持っているかどうか
- ・改ざんを防止するセキュリティ面での安全性が担保されているかどうか
PDF化された契約書は有効?
Adobe(アドビ)社が開発し、ビジネスシーンで多く使われるようになった「電子文書」のファイル形式であるPDF(Portable Document Format/ポータブル・ドキュメント・フォーマット)。現在、PDF化された契約書は、電子署名法第3条に基づき、電子署名が施されていれば法的に有効だとされています。
近年では多くの企業や個人で利用されているPDFは電子署名に最適なフォーマットであり、契約書の信頼性や法的な有効性を確保しやすいものだといえます。
【より詳しく知りたい方は、以下の記事へ】
引用元:PDF ファイルで電子署名を利用する方法 (Acrobat /Acrobat Reader)
タイムスタンプの必要性
「電子帳簿保存法」では、電子データでの保存を認める要件に、その電子データが改ざんされていない原本書類であることを担保する必要があるとされています。そのために開発されたタイムスタンプは、第三者機関である時刻認証局(TSA/Time Stamping Authority)が発行することが必要であるため、原本書類にタイムスタンプが付与されていれば、改ざんされていないと証明されたことになるわけです。
ただ2022年1月1日には「電子帳簿保存法」が大幅改正され、以下の電子データはタイムスタンプが不要となっています。
- ・電子帳簿保存法に対応したクラウドシステム
- ・電子データの訂正や削除の履歴と内容を確認可能
- ・送信者側にタイムスタンプが付与
- ・受信者側がデータを自由に訂正や削除できないシステム
- ・訂正や削除を防止する事務処理規程
【より詳しく知りたい方は、以下の記事へ】
タイムスタンプとは?タイムスタンプの必要性やメリット、電子署名との関係を解説
今後ますます普及が見込まれる電子契約
2025年1月現在、日本の自治体における電子契約の普及率は、合計約370自治体となっており約20%を超えています。今後さらなる普及の高まりも見込まれており、DXを推進している政府・総務省によると、一般財団法人 日本情報経済社会推進協会/JIPDEC(ジプデック)が調査した「企業IT利活用動向調査2024」(2024年1月時点)では企業の利用率は77.9%にも上っています。そして、近年主流となっているクラウド型電子契約システムの普及により、さらなる進展が見込まれています。
【より詳しく知りたい方は、以下の記事へ】
国内20社以上 各社サービスのご紹介
おすすめ電子契約3選
01操作が簡単で安い!クラウドコントラクト

中小企業や個人事業主向けの電子契約サービス。業界最安値クラスの導入しやすいお手頃価格と、操作が簡単ですぐに使いこなせるシンプルな機能が特徴です。
| 対象 | 月額料金 | プラン数 | お試し |
|---|---|---|---|
| 個人 法人 |
2,178円~ | 3個 | 無料 |
02高機能な有名サービスクラウドサイン

業界内で高い知名度を持つサービス。大手企業のニーズに答える豊富な機能をそろえています。
| 対象 | 月額料金 | プラン数 | お試し |
|---|---|---|---|
| 個人 法人 |
11,000円~ | 4個 | 無料 |
03カスタマイズ機能が豊富GMOサイン

オプション機能が豊富で、自社のニーズに合わせて機能をカスタマイズできるサービス。主に大企業向け。
| 対象 | 月額料金 | プラン数 | お試し |
|---|---|---|---|
| 個人 法人 |
8,800円~ | 4個 | 無料 |