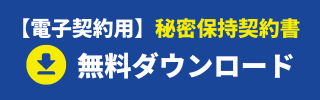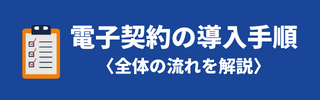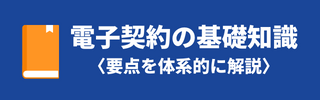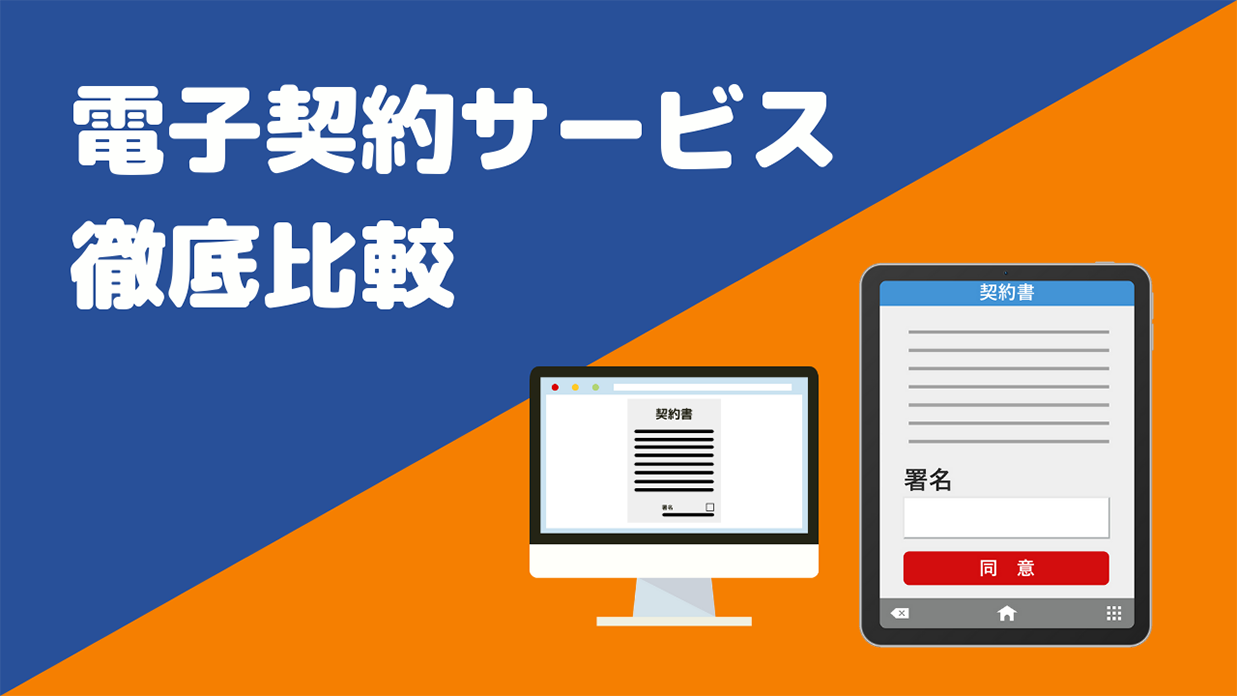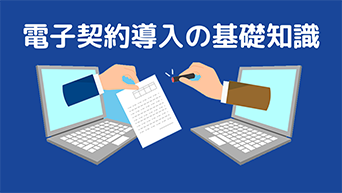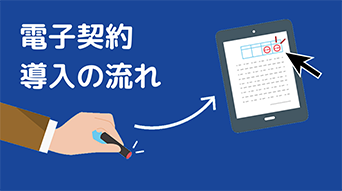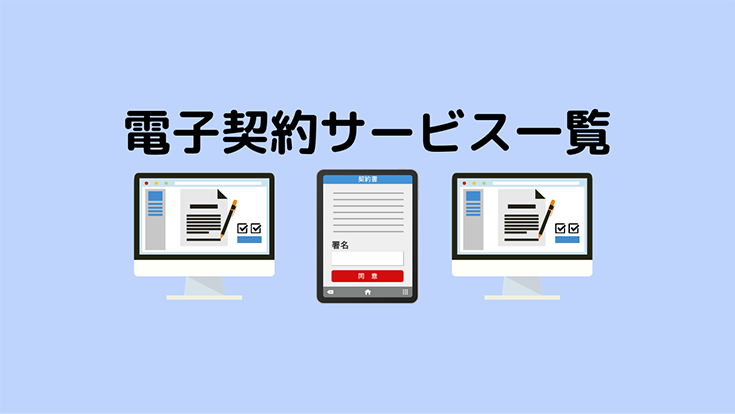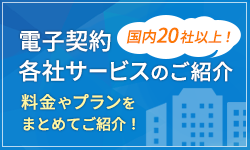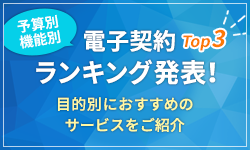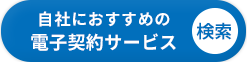2024年06月04日2025年11月21日
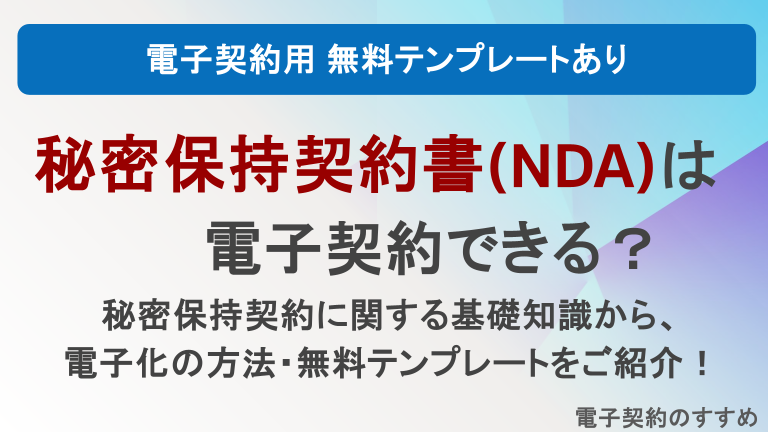
秘密保持契約書(NDA)とは
秘密保持契約とは、技術情報や顧客情報、経営情報などを他社に開示する際に、開示した情報の目的外の利用を禁止したり、第三者に開示・漏洩をしないよう、適切な情報管理を義務付ける契約です。
秘密保持契約書は、この秘密保持契約を結ぶための書面となり、ビジネスシーンにおいては、英語で秘密保持契約を指す「Non Disclosure Agreement」の頭文字を略した「NDA(エヌディーエー)」とも呼ばれています。
この秘密保持契約書(NDA)は、通常の新規取引等で使用されるような「取引基本契約書」「雇用契約」「業務委託契約書」など、契約・取引内容に関わる契約書とは別で締結するケースが多いものとなります。
秘密保持契約書(NDA)の基本項目
秘密保持契約の契約書では、基本的に以下のような項目が盛り込まれます。
| 1 | 目的 |
|---|---|
| 2 | 秘密情報の定義づけ |
| 3 | 秘密保持義務 |
| 4 | 目的外利用の禁止 |
| 5 | 秘密情報の管理方法 |
| 6 | 秘密情報の返還・廃棄義務 |
| 7 | 損害賠償 |
| 8 | 契約期間 |
| 9 | 適用除外 |
| 10 | 知的財産権の不付与(知的財産権の帰属) |
| 11 | 反社会的勢力の排除 |
| 12 | 準拠法および合意管轄 |
秘密保持契約書(NDA)の記載例
1.目的
契約を締結する目的を明確にし、どのような情報交換や協力関係のために秘密情報を開示・受領するのかをこの項目で定めます。
例文
甲(情報提供者)が乙(情報受領者)に対して、〇〇プロジェクト(例:共同研究、事業提携、業務委託など)に関する機密情報を開示するにあたり、その取扱いについて秘密保持義務および目的外利用の制限を定めることを本契約の趣旨とします。
2.秘密情報の定義づけ
ここが非常に重要です。「何が秘密情報なのか」を具体的に定める項目です。口頭でのやり取りから書面、データまで、どんな情報が対象になるのかを明確にします。同時に、既に世に出ている情報など、秘密情報に含まれないケースもきちんと示しておきましょう。ここが曖昧だと、後々「言った言わない」のトラブルになりかねません。
例文
本契約において『秘密情報』とは、甲が乙に対し、開示手段のいかんを問わず提供する、技術・営業・財務・顧客・人事・ノウハウなどの非公開情報全般を指します。ただし、次に掲げる情報は含まれません。」
「秘密情報を開示する際には、当該情報が秘密である旨を明示するものとします。書面には『秘密』と表示し、口頭による場合はその旨を告げ、原則として〇日以内に書面で補足通知を行うものとします。
3.秘密保持義務
秘密情報を受領した側(受領者)が、どのように情報を保護すべきかを記します。
経済産業省が発表しているひな形では、5項目にわたって秘密情報を取り扱う人の範囲や、関係会社への情報開示などを記した例が記載されているのでぜひご参考下さい。
参照:秘密保持契約書ひな形(経済産業省)
例文
乙は、甲から開示された秘密情報を厳に秘密として保持し、甲の事前の書面による承諾なくして、第三者に開示、漏洩し、または複製してはならない。
4.目的外利用の禁止
開示された秘密情報は、この契約で合意した目的以外に使うことを約束させます。例えば、共同開発のために得た情報を、自社の別の事業に無断で利用するような行為を禁止するわけです。
例文
乙は、開示された秘密情報を、本契約の目的達成のためにのみ使用し、その他の用途に利用してはなりません。
5.秘密情報の管理方法(あれば)
受領者による秘密情報の管理の仕方や、情報へのアクセスを許容する範囲を定めています。
例文
乙は、受領した秘密情報について、自社の重要情報と同等以上の注意を払って適切に管理し、善管注意義務をもって取り扱うものとします。」
「乙が秘密情報へのアクセスを認める者は、契約目的の遂行に必要最小限の役職員に限定し、当該者にも同様の秘密保持義務を課すものとします。
6.秘密情報の返還・廃棄義務
契約が終了した時や、情報の開示元(開示者)から求められた場合に、受け取った秘密情報(コピーも含む)をどう扱うかを決めます。速やかに返却するのか、それとも責任を持って破棄するのか、その手順を明確にしておきます。
例文
乙は、契約終了時または甲からの請求があった場合、秘密情報およびその複製物をすみやかに返却または破棄し、その実施状況を文書で報告しなければなりません。
7.損害賠償
もし秘密保持の約束を破り、情報が漏れてしまった場合にどうなるかを定めます。これにより、情報漏洩によって生じた損害(失われた利益なども含め)を、違反した側が賠償する責任があることを明確にします。
例文
万一、乙が本契約に違反して情報を漏洩し、甲に損害が生じた場合、乙はその損害(間接的損失を含む)を賠償する責任を負います。
8.契約期間
このNDAがいつからいつまで有効なのかを定めます。ただし、秘密保持の義務は、契約期間が終わった後も一定期間(例えば3年など)続くのが一般的です。重要な情報ほど、長く義務を継続させるべきでしょう。
例文
本契約の有効期間は締結日から〇年間とし、秘密保持義務については契約終了後もさらに〇年間継続するものとします。
9.適用除外
既に世の中に公開されている情報など、特定の情報は秘密保持の義務から外れることを改めて明記する項目です。「秘密情報の定義」で触れていても、念のため独立した条項として設けることがあります。
例文
以下に該当する情報は秘密情報の対象外とします。
1.開示前から既に乙が保有していた情報
2.開示時に公知であった情報
3.開示後、乙の責に帰すことなく公知となった情報
10.知的財産権の不付与
NDAを結んで秘密情報を開示したからといって、その情報に含まれる特許や著作権などの知的財産権が、自動的に情報を受け取った側に移るわけではないことを明確にします。ただし、その後の協力関係によっては、柔軟な取り決めも可能です。
例文
本契約は、秘密情報に含まれる特許・著作権などの知的財産権を乙に譲渡または許諾するものではありません
11.反社会的勢力の排除
契約を結ぶ双方が、反社会的勢力と一切関係がないことを宣言し、もし関係が判明した場合には契約を解除できる旨を定めます。コンプライアンス遵守の観点から重要な条項です。
例文
甲および乙は、現在また将来にわたり反社会的勢力と一切の関係を持たないことを相互に表明し、これを保証します。
12.準拠法および合意管轄
万が一トラブルが起きた際に、どの国の法律に基づいて解決するか(準拠法)、そしてどこの裁判所で争うか(合意管轄)をあらかじめ決めておきます。これにより、紛争解決をスムーズに進めることができます。
例文
本契約に関する準拠法は日本法とし、契約に関連する紛争は〇〇地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
秘密保持契約書(NDA)は印紙税の対象になる?
秘密保持契約書は、印紙税法で定められた20種類の課税文書に該当しない為、基本的に印紙が不要です。
秘密保持契約書の主な目的は、「秘密情報の開示・利用方法の取り決め」であり、物品の売買やサービスの提供、金銭の貸し借りといった「経済的取引そのもの」を目的とした契約ではなく、あくまでメインの契約の前提として、情報管理のルールを定める補助・補完的な役割を果たすことがほとんどとなるため、秘密保持契約書単体では、印紙税の対象となる文書には当たらないと解釈されています。
参照:国税庁HP 印紙税額の一覧表(第1号文書から第20号文書まで)
*印紙税が必要になるケース
ほとんどの秘密保持契約書は非課税ですが、稀に、記載内容によっては課税文書とみなされる場合があります。 もし秘密保持契約書の中に、以下のような項目が強く盛り込まれている場合は、注意が必要です。
【1】特定の業務を「請け負う」要素が色濃い場合:
秘密情報の開示が、単なる情報共有にとどまらず、「〇〇という成果物を必ず作り上げ、その対価を支払う」という内容の場合です。まるで請負契約書そのもののような性質を持つNDAは、印紙の対象となる可能性があります。
【2】「継続的な取引の基本契約」としての側面がある場合:
単なる秘密保持だけでなく、将来にわたる取引関係の土台となるような、継続的な情報提供やサービスに対する報酬のルールなどが明記されているNDAも、印紙税法上の「第7号文書」に該当すると判断されることがあります。
一般的な「情報漏洩を防ぐ」ことに主眼を置いたNDAであれば問題ありませんが、上記のような特殊なパターンでは、NDAが別の課税文書と判断される可能性があるため注意が必要です。
秘密保持契約書(NDA)を他の契約書に統合できる?
結論から言うと、秘密保持に関する条項は、メインとなる他の契約書(例:業務委託契約書)の中に組み込んで統合することが可能です。
ただし、統合する場合でも、NDAに必須の項目を漏れなく、かつ明確に記載することが非常に大切になります。
また通常、複数の契約書をまたぐプロジェクトや、契約交渉の初期段階で機密情報のやり取りが必要な場合は、単独のNDAが望ましいです。ただし、内容をしっかり盛り込めば、統合は有効な選択になります。
*統合する場合のポイント
先程記した項目を押さえることがベストですが、以下のポイントを特に確認することが重要になります。
①秘密情報の定義を明確にする
何が秘密情報に該当するのか、文書・口頭・電子データなど開示手段を問わず、具体的に規定しておくことで、認識のズレや後のトラブルを防げます。
②第三者への開示制限を記載する(情報のアクセス制限)
業務委託先や子会社などに情報を共有する必要がある場合は、どの範囲まで開示が許容されるか明文化しておきましょう。
③契約終了後の取り扱いを明記する(情報の返還・廃棄)
契約終了後に秘密情報を返還・廃棄する義務や、秘密保持義務が継続する期間を明記することで、情報漏洩リスクを軽減できます。
④目的外利用の禁止を含める
秘密情報を契約目的以外に使用しないことを明確にし、使用範囲を限定することが必要です。
⑤他の条項と整合性を保つ
損害賠償や知的財産の取り扱いなど、他の条項との矛盾が生じないよう、文言や位置づけに注意しましょう。
以上の点を踏まえれば、NDAを本契約に統合しても、実務上のリスクを最小限に抑えつつ、効果的な情報管理が可能になります。
秘密保持契約書(NDA)は電子契約できる?
秘密保持契約書(NDA)は、特に法律で「書面で契約を行うこと」は定められていないため、電子化が可能な契約書となっています。
秘密保持契約書(NDA)のメリット
秘密保持契約(NDA)を電子化するメリットは、他の契約書の電子化と同じとなりますが、印刷や郵送、捺印・返送を待つ必要もなくなるため、契約完了までのスピードアップ、契約業務の効率改善・コスト削減が見込める点です。
印紙税に関しては、秘密保持契約(NDA)は、印紙税法上の課税文書ではないため、書面契約でも基本的には、印紙税は発生しませんが、業務請負に関する内容と秘密保持契約の内容をまとめた「秘密保持契約書(NDA)」を使用される場合などには、課税文書に該当しますので、書面契約では印紙税が必要となります。
もし、業務請負に関する内容を含む「秘密保持契約書(NDA)」を使用する場合は、電子契約を行うことで印紙税削減も大きなメリットとなります。
秘密保持契約書(NDA)の電子化する方法
秘密保持契約(NDA)を、書面契約ではなく、電子契約で結ぶことによって、大幅に契約書の内容を変更する必要はないため、基本的には現在使用している書面を微調整すれば、使用することができます。
以下が、変更ポイントとなります。
変更ポイント
「書面による承諾」等の記載がある箇所の文言を変更
例:書面:書面による承諾が無い限り
電子契約:書面または双方が合意した電磁的措置による承諾が無い限り
末尾文言(本契約の成立の証として、以降)を変更
例:書面:本書2通を作成し、各自記名押印の上、各1通ずつ保有する。
電子契約:本電子契約書ファイルを作成し、それぞれが電子署名を行う。
なお、本契約においては、電子データである本電子契約書ファイルを原本とし、同ファイルを印刷した文書はその写しとする。
押印欄を削除(任意)
電子契約では、押印・捺印は不要となるため、電子契約サービスを使用する場合は、契約相手の操作の負担になる可能性も考慮しできるだけ削除したほうが良いでしょう。
※これはあくまでも契約相手への考慮となるので、本来は押印・捺印が不要な電子契約でも、契約をした目印にしたい等の場合は削除せずとも問題ありません。
秘密保持契約書(NDA)のよくある質問
秘密保持契約書(NDA)は、いつだれが作る?
NDAは、秘密情報を開示する前に、情報を開示する側(情報開示者)が作成するのが基本です。しかし、情報受領者側からNDAの締結を求めることも可能です。大切なのは、情報共有を始める前に双方が合意することです。
秘密保持契約書(NDA)は印紙が必要?
一般的なNDAでは、印紙税法で定められた課税文書に該当しないため、収入印紙は不要です。ただし、契約内容に請負や継続取引の要素が強く含まれる場合は、印紙が必要となるケースもあります。
守秘義務契約書と秘密保持契約書の違いは?
実質的な違いはほとんどなく同じと捉えても問題ありません。どちらも「秘密情報を外部に漏らさない義務」や「目的外に利用しない義務」を定める契約書を指します。一般的には「秘密保持契約書(NDA)」という名称が広く使われています
秘密保持契約書と秘密保持誓約書の違いは?
主な違いは「契約形態」になります。秘密保持契約書は、企業同士など対等な立場で互いに義務を負う「双務契約」が一般的です。一方、秘密保持誓約書は、主に従業員が会社に対して秘密を守ると「誓う」形で、義務を負うのは従業員側のみの「片務契約」となることが多いです。
秘密保持契約(NDA)は3者間など複数者間でも交わせる?
可能です。 複数の企業や個人が関わるプロジェクトでは、情報の共有元・共有先が多岐にわたるため、3者間以上の複数者間でNDAを締結するケースがございます。各当事者が秘密保持義務を負うことで、情報漏洩のリスクをより広範囲でカバーできます。
秘密保持契約書(NDA)に保管期限はある?
秘密保持契約書自体に直接的な保管期限は定められていません。しかし、税法や会社法で定められた帳簿書類の保管義務(通常7〜10年)に準じて保管することが一般的です。また、秘密保持義務の有効期間が終了した後も、契約の証拠として適切に保管することが推奨されます。
秘密保持契約書(NDA)を他の契約書に統合することはできる?
はい、秘密保持契約書(NDA)は、業務委託契約書など、他の契約書に統合することが可能です。ただし、秘密情報の範囲や保持義務の内容が明確になるよう、条項を十分に整備することが重要です。
秘密保持契約書(NDA)はなぜ必要?
新しい取引や協業の際に、お互いの大切な技術や顧客情報などが外部に漏れるのを防ぐためです。また、お互いの関係性を確認し信頼関係の土台を築く重要な役割を果たします。
秘密保持契約書(NDA)の内容に違反した場合はどうなる?
NDAに違反し情報漏洩などが起きた場合、差止請求や損害賠償請求が行われる可能性があります。情報開示側は、漏洩によって被った損害を請求でき、企業の信用失墜にも繋がります。また、悪質な場合は不正競争防止法違反で刑事罰の対象となる可能性もあります。ただし、判例は少なく契約解除を取られることが一般的です。
秘密保持契約書(NDA)は電子契約できる?
はい、電子契約可能です。以前は紙での契約が多かったですが、文書のチェックや修正が容易であること、また契約締結までのスピードが早いといったメリットがあるため導入が進んでいます。
秘密保持契約書(NDA)は電子帳簿保存法の対象になる?
経済取引における契約書でないため、通常の取引では保存法の対象とはなりませんが、他契約書と同様に管理するのをおすすめします。契約書を統合した場合や契約違反により損害賠償金を請求・支払する場合には資金の流れに直結する契約書に該当してしまうためです。
秘密保持契約書(NDA)向きの電子契約サービスはある?
「NDA対応」と明確に記載があるGMOサインやマネーフォワードクラウド契約などがおすすめです。その他、契約書のテンプレート提供、複数者間での署名機能、文書の安全な保管、検索機能など、NDAに必要な機能を備えたサービスを探してみるのもよいでしょう。
秘密保持契約書(NDA)の電子契約用無料テンプレート
さて、ここまで、秘密保持契約(NDA)について、電子化のメリットや方法をご紹介しましたが、いかがでしたでしょうか?
既に自社の秘密保持契約書(NDA)をお持ちの方は、書類の内容を少し調整するだけで簡単に電子契約で使用できますので、当記事をお役立ていただければ幸いです。
これから自社の秘密保持契約書(NDA)の作成をされる方もご安心下さい!
当サイトでは、電子契約用に調整した契約書テンプレートをご用意しておりますので、ぜひこちらもご活用頂ければ幸いです。
※上記ファイルは、あくまでも電子契約用に調整した契約書のサンプルとなりますので、ご利用については弊社では責任を負いかねます。必ず専門家へご相談頂き、内容を自社用に変更・カスタマイズした上でご使用下さい。
電子契約サービスの選び方
電子契約をこれから選ぶ方は以下ページもぜひご覧ください!
おすすめ電子契約3選
01操作が簡単で安い!クラウドコントラクト

中小企業や個人事業主向けの電子契約サービス。業界最安値クラスの導入しやすいお手頃価格と、操作が簡単ですぐに使いこなせるシンプルな機能が特徴です。
| 対象 | 月額料金 | プラン数 | お試し |
|---|---|---|---|
| 個人 法人 |
2,178円~ | 3個 | 無料 |
02高機能な有名サービスクラウドサイン

業界内で高い知名度を持つサービス。大手企業のニーズに答える豊富な機能をそろえています。
| 対象 | 月額料金 | プラン数 | お試し |
|---|---|---|---|
| 個人 法人 |
11,000円~ | 4個 | 無料 |
03カスタマイズ機能が豊富GMOサイン

オプション機能が豊富で、自社のニーズに合わせて機能をカスタマイズできるサービス。主に大企業向け。
| 対象 | 月額料金 | プラン数 | お試し |
|---|---|---|---|
| 個人 法人 |
8,800円~ | 4個 | 無料 |